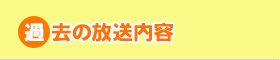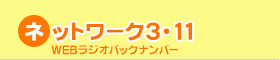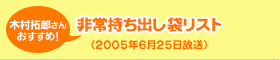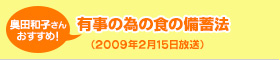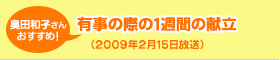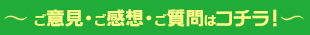ゲスト:大阪市港区まちづくりセンター 防災アドバイザー 多田裕亮さん

「大阪・関西万博」の開幕からおよそ3か月。連日、多くの外国人が大阪を訪れています。もし、万博開催中に大きな地震が起こったら、地震や津波の怖さを知らない外国人観光客をスムーズに避難誘導できるのでしょうか。
「ゼッタイに楽しめない茶道体験」は、外国人に日本の伝統文化"茶道"と、突然起こる"地震"を同時に体感してもらおうという新しい試みです。参加者は、畳を敷いた起震車でお茶とお菓子を楽しんだ後、そのまま震度7の揺れを体験することになります。
これは大阪市港区が公民連携で取り組む「おもてなし防災」プロジェクトの一環です。「おもてなし防災」では、英語版の避難誘導ポスターや災害啓発ポスターをつくり、SNSで防災情報を発信するなど、外国人観光客に防災意識を持ってもらい、さらに「外国人の避難誘導ができる市民」を増やすことを目指しています。番組では、このプロジェクトに取り組む大阪市港区まちづくりセンターの防災アドバイザー、多田裕亮さんに外国人に向けた防災対策について話を聞きます。
おもてなし防災(OMOTENASHI BOSAI)
https://omotenashi-bosai.jp/
(番組内容は予告なく変更する場合があります)