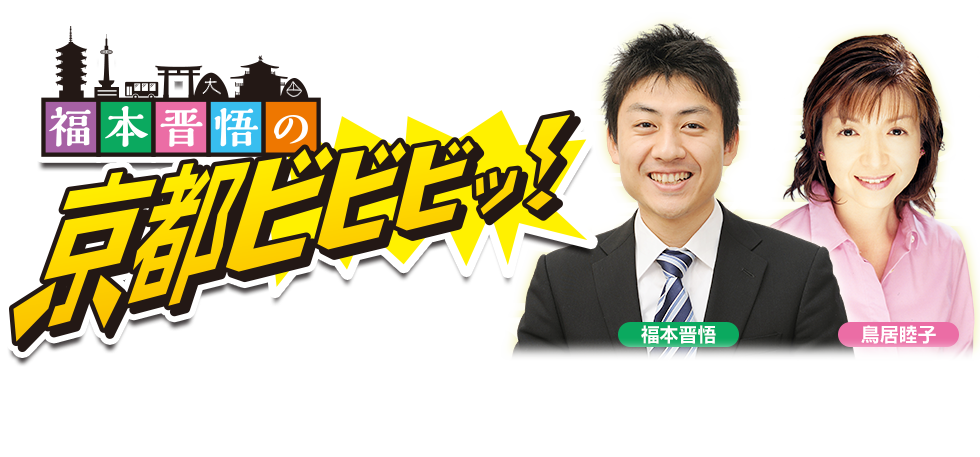

2021年最後の「京都ビビビッ!」
12月ということで、スタジオもクリスマス飾りが・・・
「京都の通り、ひととおり」は、今回で8通り目!
「御池通り」をご紹介しました。
今回もたくさん歩いた福本アナ。
詳しくは、福本アナウンサーの取材日記で!
2つ目のコーナーでは「京の老舗が挑む 新展開グルメ」をご紹介。
①まずは今年の4月に四条烏丸にオープンした豆乳カフェ「 EVERYSOY 」。
「ソイ」とは英語で「大豆」。
このお店の運営は、明治18年(1885)創業の老舗「ゆば庄」さんがやっているんです。
「 EVERYSOY 」からは「ソイビスコッティ」と「ソイティラミス」をご紹介。「ソイビスコッティ」は、小麦粉を大豆の粉に置き換えたたことで、焼き上がりがまったく違い、カリッとした歯ごたえのある食感を出すのが難しかったんだとか。そこで3度焼きすることで、その食感を表現することに成功。
さらに、栄養価を高めるために、ナッツやドライフルーツをふんだんに使っているんだそうですよ。
(1本200円税込。味はプレーン/抹茶/ココア)
「ソイティラミス」は乳製品不使用とは思えないクリーミーさと、植物性ならではの軽さを表現しているそうです。(1個648円税込)
【EVERYSOY】
住所:京都市下京区函谷鉾町101 LAQUE(ラクエ) 四条烏丸 1F
京都市営地下鉄烏丸線「四条」駅/阪急京都線「烏丸」駅 22番・24番出口直結
②続いては、去年の8月、四条河原町にできた、発酵を楽しむ「AMACO(アマコウ)CAFE」。このお店は「京つけもの西利」さんが運営しているんです。
「AMACOCAFE」からは みみまでやわらかい「AMACOBREAD甘麹熟成食パン」(1本1296円税込)としっとりしていながら軽い食感に仕上げた「甘麹パウンドケーキ(丹波黒豆)」(1本2808円税込)をご紹介。
発酵を極めた西利が作った「乳酸発酵甘麹(あまこうじ)」を使用した体と心が喜ぶパンやスイーツなんだそうです。
【AMACO CAFE】
住所:京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町310-2
立誠ガーデンヒューリック京都1階(元・立誠小学校跡)
阪急「京都河原町駅」徒歩3分
③最後にご紹介したのは、1864年創業、老舗和菓子店の「伊藤軒」さんと、
地下足袋や作務衣などを現代風にアレンジして制作している京都のアパレルブランド「sou・sou(ソウソウ)」さんとのコラボ店、「伊藤軒/SOU・SOU 京都清水店」。
今年の9月に、清水産寧坂にオープンし、その可愛らしいビジュアルから若い女性に大人気!
「伊藤軒/SOU・SOU 京都清水店」からは 「串和菓子」(1本500円税込)をご紹介。(2種類:「季節」「sou・sou」)
見た目にもかわいい「串和菓子」は串にささっているので、食べ歩きにもぴったりですよ。
【「伊藤軒/SOU・SOU」京都清水店】
住所:京都市東山区清水3丁目315(3分歩けば清水寺)
皆さんはどれが食べてみたいですか?
そして「シンゴのビビビッときたぞ!」では
一足早く、来年の干支、「寅」にまつわるスポットをご紹介。
12月中に行くも良し、もちろん新年明けてから行くも良し
京都に行かれる方は、参考にしてくださいね♪
詳しくは、福本アナの取材日記で!
2021年も「京都ビビビッ!」をお聴きいただきありがとうございました。
次回放送は、来年の2月14日(月)午後8時からの予定です。
皆さまが知りたい京都の通りも引き続き募集しています!
kyoto@mbs1179.com
では皆さま、良いお年を!!

おかげさまで第40回を迎えた京都ビビビッ!今回もいつもどおりいっぱい京都を歩いて取材をしました。
「京都の通り、ひととおり」では、御池通りを歩きました。
東は鴨川のすぐ東隣の川端通から、西は太秦までの約5キロの通りです。
鴨川を渡ると、広い御池通があります。道幅50m(車道が26m、12mの歩道が2つ)もあります。電線や電柱は地中化され、一定間隔にケヤキの木が植えられています。さらに、車道の照明と交通標識と信号機と、交差する通り名の標識を一体化したデザインが統一された灰色の柱があります。
河原町御池、つまり京都市役所前には、本能寺があります。本能寺の変として、あまりにも有名ですが、その時の本能寺は、蛸薬師通油小路(四条堀川に近い)のところで、現在の場所ではありません。後に豊臣秀吉による都市計画で現在の場所へ移転となり、当時は今の京都市役所を含んだ広い敷地だったそうです。
境内に入るととても静かで驚きました。河原町通側にも御池側にも8階建てくらいのビルに囲まれているので、道路からの騒音が遮られています。
織田信長の三男・信孝によって建てられた信長の供養塔があります。石塔の下には、信長が使った刀が眠っているそうです。
その横には、高さ6階くらいある大きなイチョウの木があり、イチョウの落ち葉が信長の供養塔のあたり一面を黄色に染めていました。このイチョウの木、幕末の蛤御門の変の火災の時に、この銀杏の木から水が噴き出し火を消したという逸話があります。
ところで、本「能」寺は、建立から現在まで5度の火災に見舞われてきたため「能」の右の「ヒ」を使わず、ヒが「去る」ように、字を変えて使っていと言われています(諸説あり)。
境内は無料でお参りできますが、信長やお寺の貴重なものがある宝物館は、500円で見学できます。
そもそも、御池通は、元々平安京ができた時は三条坊門小路でした。大きな道になったのは、第二次世界大戦末期の1945年に御池通りの南側の民家に対して、空襲で燃え広がるのを防ぐための建物疎開が行われたためです。結果として、戦後(1947年)に、幅50メートルの幹線道路となったのです。
堀川御池までは片側2車線以上でしたが、それより西は片側1車線の道になります。御池通りの名前の由来は堀川通りの西にあります。
それは、神泉苑です。神泉苑の池に通ずる道だから江戸時代中期に御池通と呼ばれるようになったという説が通説になっています。神泉苑は、平安京ができた時、大内裏のすぐ南東隣に位置する天皇のための庭でした。当時は東西およそ250m、南北500mのおよそ3万坪もあったが、江戸時代に家康が二条城をつくることになり、広さが1/16になりました。
現在は、東寺真言宗のお寺ですので、御朱印もあります。御朱印帳に書いていただけるものだけで9種類あります。さらには、期間限定や書置きも色々な種類があります。
神泉苑を出て、西に500mほど進むと、千本御池つまりはJR二条駅です。二条駅の西側に御池通りを示す看板があるので、続いていることは事実です。しかし、実は北に130m進んだところの交差点から西が御池通りで、そこから御池通りが南西方向に斜めに再スタートしているのです。つまり御池通りが、一筋北に通りがずれているんです。一本北は押小路通りですが、押小路通はこの交差点で終点。ここの交差点の名前を示すものはありませんでした。
西にどんどん進みましょう。西大路通りを越えると、島津製作所の本社や工場のあり、通り過ぎると、京都を代表するパン屋さん志津屋の本店もあります。昭和23年に河原町通六角に開業し、昭和57年に新本社工場とその隣に本店ができました。出来立てのパンがすぐに届くそうですよ。
どんどん西に行くと、学校が見えてきました。いつもこの番組で京料理をつくってくださる宗川裕志先生がいらっしゃる大和学園・京都調理師専門学校が右手に。左手には、京都の通り名の唄について教えてくださった鍛治宏介先生のいる京都先端科学大学があります。
さて、御池通り、ゴールは、太秦です。交差点名は「三条御池」。おかしいと思いませんか?実は三条通が北西方向に斜めになっているため、本来なら東西真っすぐの道路同士なのに交差点になっているんです。
三条御池は、嵐電天神川駅と地下鉄太秦天神川の場所で、御池通りのほとんどは、道路の下に地下鉄東西線が走っています。御池通りは約5キロ。歩くのはしんどいという方は地下鉄の一日券で散策を笑
「シンゴのビビビッ!っときたぞ」では、寅年初詣をご紹介しました。
2022年は寅年。思い起こせば、去年の今頃は、初詣を12月中に先取りする「幸先詣(さいさきもうで)」というワードが登場しましたね。元から私は毎年言っていますが、わざわざ年始にその年の干支にまつわる神社に、寒い中3時間とか並ぶことは、ナンセンスだと思っている分散参拝派です。であれば、寅にゆかりのある神社を12月中にお参りしてもいいのではと思っています。ということで、寅にまつわるスポットを3か所ご紹介します。
(1)両足院の毘沙門堂
祇園の花見小路をさがったところにある建仁寺。その塔頭の1つが両足院です。境内には、毘沙門天をまつる毘沙門天堂があります。毘沙門天が現れたのが「寅年・寅月・寅日・寅刻」だったとされることから、毘沙門天のお使いは虎といわれています。毘沙門天堂には狛寅があります。もちろん、右の狛虎は口を開けて、左は閉じていて、阿吽になっています。
授与所には、寅に関するものも色々あり、寅守(500円)黄色い虎2匹が描かれています。
虎みくじ(500円)がかわいいです。高さ4センチくらいの手乗りサイズの虎の焼き物の中に、おみくじが入っています。
絵馬は、虎が描かれたものが2種類あります。絵馬をかけるところにはたくさんありました。ジャニーズジュニアの7人組グループTravis Japan(トラビス ジャパン)が、10月に南座で3週間公演をされたこともあり、ファンの皆さんが「千秋楽まで無事に駆け抜けられますように」や「寅年の来年にデビューできますように」などの願いが書かれていました。来年、ファンの皆さんの願いが届きますように。
毘沙門天堂と授与所はいつでもお参りできますが、両足院は、座禅体験などを除いて、普段は方丈やお庭などは非公開のお寺です。お正月の特別公開は、1月1日~11日(月・祝)です。
ちなみに、毘沙門天を本尊として祀ったのがはじまりとされる鞍馬寺にも虎の授与品があります。正月期間限定ですが、1800円で「阿吽の虎」の置物が授与されるそうです。
(2)松尾(まつのお)大社。
阪急嵐山線の松尾(まつお)大社の駅からすぐ、松尾大社です。平安京ができる前の701年創建され、古くからお酒の神様としての信仰も集める神社です。
北は玄武、南に朱雀、東は青龍、西に白虎という四神相応之地(しじん・そうのうのち)は、地形としては、玄武は船岡山、朱雀は巨椋池、青龍は鴨川、白虎は山陰道ですが、神社では、玄武は上賀茂神社、朱雀は城南宮、青龍は八坂神社、白虎は松尾大社です。さらに平安神宮とあわせて、京都五社ともいわれます。
という訳で、白虎の松尾大社です。拝殿には、高さ3m以上、横は5m以上もある絵馬が掲げられ、白い虎に盃、松竹梅、神の使いとされる亀が描かれていました。
白虎おみくじがあるんですが、コロナ禍のため現在品切れ。お正月には間に合うとのこと。
御朱印は、通常の物は300円ですが、500円で白虎朱印もあります。現在は、書置きのみの対応ですが、松尾大社の御朱印帳を新たに購入される方は直接書いていただけるそうです。もちろん白虎のデザインで、猛々しい虎とかわいいバージョンがあります。
(3)京都市動物園
最後は、本物の虎を見に行きましょう!明治36年にできた京都市動物園は、日本で2番目にできた動物園です。ロシアのアムール地方や中国東北部に生息するアムール虎を2匹飼育しています。寒い地方の虎なので、寒い京都ですが、むしろ寒い時期が元気です。実は、虎を含めたネコ科動物にもコロナ感染の恐れがあるということで、現在は柵から2mほど離れての見物になっています。オスがオク君、その母がアオイちゃんです。
京都市動物園の飼育員・虎担当の河村あゆみさんによりますと、虎は日中寝ることが多いんですが、収容といって部屋の中に入ってご飯を食べる時間に近づいてくるとうろうろすることが増えてくるそうです。
オク君は、は立ち上がった時の高さは、2m30センチ、体重150キロと迫力があります。年賀状の写真にしてはいかがでしょう?僕はそうします。
京都市動物園は、月曜と12月27日~1月1日がお休みで、年明けは1月2日からです。
寅年にまつわるスポットをご紹介しました。どうぞ、良い年をお迎えください。
【シンゴが選んだ京都の曲】
M1 アケチノキモチ feat.阿部sorry大臣ちゃん / レキシ
本能寺を訪れましたので、この曲を。放送では1番まででしたが、ぜひフルコーラスでアケチノキモチを感じてください。
【バックナンバーカレンダー】

