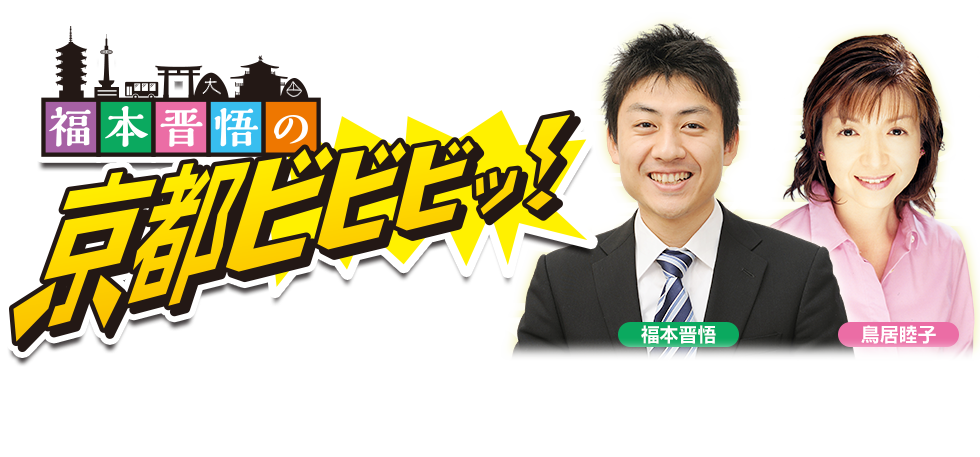

12月28日で、京都タワーは開業52年を迎えました。
開業した1964年(昭和39年)は、東京オリンピックや東海道新幹線開業の年で、タワー展望室の営業が始まったのがこの日です。
実は、当初はタワー計画ではありませんでした。
京都駅と地下でつながるデパートを計画されましたが、意外にも当時の京都駅の利用客が少なく許可が下りなかったそうです。
結局、9階までがホテルやレストラン、当時のデパートが入る建物になり、その上にタワーが乗っかっている構造で、高さ131メートルの建物が完成しました。
京都タワーは、灯台をイメージしてつくられました。
「京都市内の町家の瓦葺を波に見立てて、海の無い京都の街を照らし続ける灯台」と京都タワーの社史に書かれています。和ろうそくと思っている方も多いようです。
確かに和ろうそくのようにも見えますね。
展望室は地上100メートルです。無料の望遠鏡がそれぞれの方角に17台されていて、冬場で空気が澄んでいたら50キロ先のあべのハルカスまで見られます。
360度見わたせる眺望で、東側は清水の舞台や平安神宮の大鳥居が見えます。
地下3階にある京都タワー浴場も人気です。朝7時から夜10時まで営業されています。
昔は、寝台列車を降りた方の利用が多く、今では夜行バスに乗る方も多いそうです。
ジョギングをする人にも愛用されていています。
また、京都タワーに行けば数多くの京都のお土産が揃っています。
京都駅から帰る前に立ち寄るのもいいですね。
【アクセス、時間・料金】
JR京都駅すぐ。
タワー展望室の営業は朝9時〜夜9時までで、年中無休。
展望室の入場料は、大人770円、高校生620円などとなっています。
12月下旬になり、お正月準備の時期になりました。
今回は、京のブランド産品で、おせちに欠かせない京都の黒豆「京都府産黒大豆新丹波黒」をご紹介します。
まず黒豆との違いについてですが、かつて丹波国と呼ばれていた京都府と兵庫県にまたがる丹波地方は昔から黒大豆が特産品で、丹波で取れる黒色で大粒のものを『丹波黒大豆』と呼び、丹波以外の地域のものを『黒豆』と区別しました。
では、「新」丹波黒とは何かについてですが、「丹波黒」は、きゅうりや大根といった品目名で、「新丹波黒」は品種名です。
意味は、「京都で取れる丹波黒」のこと。
ですので、兵庫県篠山市の黒豆は「丹波篠山黒大豆」と呼ばれています。
京都府産黒大豆新丹波黒は、おせちなどでの需要が高い12月に収穫されます。
おせちに間に合わせるためには、12月20日までには店頭に欲しい。
しかし、豆を乾燥させて選別するのに1週間から10日かかるので、作業を急ぎたいところですが、皮が破れたら「腹切れ」と縁起が悪いので細心の注意を払ってされています。
紅葉の季節が過ぎ、寒さが増す12月。
この時期のイベントといえば、2005年に始まり今年で12回目を迎えた京都嵐山花灯路です。
京都嵐山花灯路は、嵯峨・嵐山地区に約2500基の行灯を点し、「灯り」や夜の散策を楽しむ観光イベントです。
平日でも6〜7万人の来場のあるイベントです。
今年は18日(日)までで、灯りの点灯時間は、夕方5時〜8時半です。
花灯路は、観光閑散期対策と夜の観光対策としてスタートしました。
まず、桜の時期の前にあたる3月に東山花灯路が。
その後、嵐山で花灯路が始まりました。
寒い時期だからこそ、『あったかいおもてなし』が合言葉です。
みどころは、やはり竹林の小径(こみち)。
竹林がライトアップされ、暖かい色に変わります。
非常に混雑するので足元に気をつけて散策をなさってください。
他にも二尊院、常寂光寺、宝厳院などお寺や神社では特別拝観やライトアップもあります。
観光客の多い京都でも冬のイベントを続けるのは難しく、また、歴史のある京都では、続けないとまわりに認めてもらえないそうです。
嵐山花灯路は12年。
今後も続けていき、伝統行事と呼ばれることを目指しています。
【アクセス】
阪急・嵐山駅、嵐電・嵐山駅が便利です。
JRは嵯峨野線・嵯峨嵐山駅が最寄りです。
京のブランド産品は京野菜だけではありません。
今回は、旬が11月〜12月中旬の「京都府産丹波大納言小豆」をご紹介します。
名前の通り、京都の丹波地方で収穫される大納言小豆です。
京都では質の高い和菓子の原料が求められ、大粒で、煮た時の香りがよく、煮崩れ(腹切れ)しない小豆が選ばれてきました。
名前の「大納言」には、大納言は切腹(腹切れ)しない高い位だからとか、大納言の烏帽子の形に由来するなどの説があります。
京都府産丹波大納言小豆の特徴は、粒が大きく、色つやがいいことです。
また、粒が揃っていて煮炊きしても型崩れしにくいので、つぶあんとして使いやすいです。そのため、一粒一粒を大切にする高級和菓子になくてはならないものになりました。
実は、全国的にみると小豆を作っている地域は多くありません。
シェアの9割は北海道。十勝が有名ですね。残り1割が近畿と東北で、近畿は京都と兵庫です、つまり丹波産となります。
寒いこの時期、温かいお茶に羊羹、おしるこもいいですね。
丹波大納言小豆に注目してみてください。

京都のこの時期といえば、大根焚ですね。
11月下旬から12月にかけて、京都のいくつかのお寺で行われる大根を焚いて振舞われる行事です。
お寺によって『だいこ』もしくは『だいこん』と読みますが、これは京ことばで大根を「だいこ」や「おだいこ」と呼ぶためです。
今回ご紹介するのは、右京区鳴滝にある了徳寺の大根焚です。
こちらでは「だいこ」と読みます。
了徳寺では報恩講(親鸞聖人の命日前後のおつとめ)にあわせて12月9日と10日に行われます。
大根焚の由来は、建長4(1252)年に遡ります。
親鸞聖人が、鳴滝の地でお念仏の教えを説かれた時、村人たちは、そのお礼にと、大根を塩味で焚いてもてなしました。
親鸞聖人はとても喜ばれ、後々の形見にと、庭のススキの穂を筆代わりにして釜の炭で、名号を残されました。
そのすすきは、今お寺の境内にあるものだと言い伝えられています。
史料では元禄時代にはすでに大根焚が行われていたそうです。
さて、大根焚の準備は、檀家さんが、前日のお昼頃から徹夜でされます。
まず、大根を3000本洗い、切ります。
外に移動し、直径1メートルの釜3つで1時間半から2時間焚きます。
昔と同じく薪を使って焚いています。
塩としょうゆで味付けし、だしを使わない大根と揚げどうふに仕上がります。
2日間で、5000人が来られるそうです。
【時間・料金】
了徳寺の大根焚は、12月9日と10日の朝9時から夕方4時まで。
大根と揚げどうふで1000円。
かやくご飯や大根の葉のおひたし、たくわんをつけると1600円。
【アクセス】
嵐電・宇多野駅から歩いて約10分。
市バス・鳴滝本町のバス停から歩いて約3分。
なお、お寺の門の前には「大根焚寺」と書かれた石碑があります。
【バックナンバーカレンダー】

