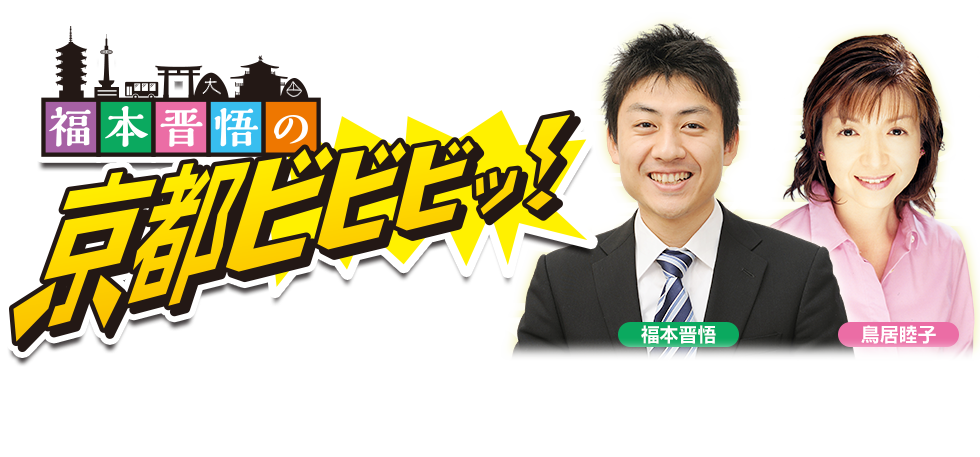

嵐山には日本唯一の小倉百人一首の博物館があります。
「小倉百人一首殿堂 時雨殿(しぐれでん)」です。
2006年1月27日に開館で、今年11周年を迎えられました。
小倉百人一首は嵐山で生まれたとされています。
今では、「百人一首」=「かるた」をイメージされる方がほとんどだと思いますが、元々は、色紙サイズで襖や壁に貼る室内装飾でした。
鎌倉時代の歌人・藤原定家の息子の嫁の父にあたる宇都宮頼綱が、嵐山の小倉山の麓に別荘を持っていて、別荘の襖に飾りをつけたいと考え、定家に歌を書くよう頼みました。
定家は、これをきっかけに歌を集めて百人一首を編纂したというわけです。
時雨殿の名前の由来ですが、宇都宮頼綱の別荘の名前が時雨亭だったので、時雨殿と名づけ、小倉というのは時雨亭のあった小倉山のことです。
なお、小倉百人一首がかるたとなったのは江戸時代ぐらいですが、誰がかるた遊びと結びつけたのかなどは分かっていないそうです。
時雨殿の1階の展示は、百人一首を詠んだ歌人の人形とともに詠んだ歌が並んでいます。
校外学習で見学する小学生の1番人気は蝉丸だそうです。やはり坊主めくりの影響ですね。
2階には、120畳の大広間があり、競技かるた大会などが開催されたりします。
おすすめは平安時代装束体験で、ボランティアの方が着せてくださいます。
私も着てみました!!
さらに本格的なものは、申込制で十二単を着て写真を撮ることができます(有料)。
【アクセス、時間・料金】
嵐電・嵐山駅から徒歩5分。阪急・嵐山駅から15分。
保津川下りの船着き場の近くです。
入館料は、高校生以上500円。小中学生は300円です。
休館日は、基本月曜日で、祝日の場合、翌火曜日が休館です。

1月中旬に色々な場所で行われるのが、左義長や「どんと」といわれる行事です。
左義長とは、1月15日つまり小正月(こしょうがつ)の火祭りです。
そもそも「正月」とは旧暦1月の別名で、本来は1月31日までを正月と呼びます。
私たちが一般的に呼ぶ正月は、元日を軸とする「大正月」(おおしょうがつ)で、1月15日を軸とするのが小正月なんです。
その小正月の火祭りを左義長や「どんと」と呼び、ほぼ全国的にみられる行事です。
地方によって、どんど焼、どんど、とんど、さんぎちょうと呼ばれています。
役目を終えた正月飾りやお札やお守り、書き初めなどを焚き上げ、この火にあたると若返るとか、餅を焼いて食べると病気をしないとか、書き初めをかざしてそれが高く舞い上がると書が上手になるなどのいわれがあります。
また、一年の始めにあたり、穢を祓い清めて、暖かい春の到来とその年の豊作を祈る行事でもあります。
大原の三千院では、15日の朝10時から1時間ほど左義長が行われます。
実は、左義長は仏教行事ではなく民間行事で、開催場所がお寺や神社であることが多いです。
三千院でも30〜40年前から地元の方と一緒に開催することになりました。
当日は、大原地区にお住まいの200世帯から注連縄などが持ち込まれますが、もちろん、どなたでも参加でき、郵送される方います。
当日は500〜600人の方が来られるそうです。
三千院では、あえて毎年1月15日に左義長をすることで本来の風習の意味を伝えたいそうです。
また、大原地区の方々とのコミュニケーションの場として大事にされています。
【アクセス】
京都バスの大原のバス停から歩いて10分。
京都駅からは約1時間。出町柳からは約30分。国際会館駅からは約20分。
拝観料は、一般が700円、高校・大学生が400円。
京都では かるた始め、蹴鞠始めなどの行事が行われていますが、弓の引き初めは、三十三間堂の通し矢・大的(おおまと)全国大会です。
今年67回目で、毎年1月15日に1番近い日曜日に開催されます。
なので、今年2017年は1月15日で、朝8時半頃から午後4時ころまで開催されます。
例年、新成人が晴れ着姿で弓を引く姿が毎年必ずといっていいほどテレビニュースで紹介されていますね。
参加できるのは、新成人と範士や教士などの称号をお持ちの方です。
通し矢の起源は諸説ありますが、本堂の縁(へり)の上から矢を放ち、的に当たった数で弓の腕の優劣を競ったことだといわれています。
また、江戸時代には、武士が、三十三間堂の軒下(約120m)で、弓の腕を競った記録があります。
さて、通し矢は、遠的(えんてき)で、的までの距離が60mあります。
普段弓道をされている方の多くは、近的(きんてき)つまり的までの距離が28mでされています。
いつもとは勝手が違うので通し矢に出場される方は、遠的ができる弓道場に何回か練習に行かれます。
矢は遠的のほうが少し軽く、羽が小さいそうです。
あとは、矢を放つ角度を上げるだけ。
私はてっきり、使う弓を変えるとか、弓の弦の張り具合とかを調整するのかと思っていたのですが、基本的に角度で調整するだけだそうです。
当日は、開会式が朝7時45分から、そしてテレビ局などの撮影用にデモンストレーションが8時頃から行われます。
これがテレビニュースで見るものです。8時半頃から男子から予選が始まります。
午後からは称号をお持ちの方の予選です。
予選では、一人あたり2本矢を放ち、2本とも的に当てた方が予選通過で決勝へ。
的の直径は予選では1mですが、決勝は79cmです。
決勝では、2本ずつ、矢を外すまで、サッカーのPK戦の延長のように勝者が決まるまで行い、男子1人・女子1人の優勝者が決まります。
年によっては、成人式と重なる場合があり、通し矢に出るために成人式に出られない学生さんもいるそうです。
予選だけだと、たった2本を射るためですが、弓道部の新成人のとっては晴れの場で、成人式と重なってしまっても成人式より優先したいという強い弓道愛を感じる行事が通し矢なんだと思います。
【アクセス】
三十三間堂へは、京阪七条駅から東に歩いて7分。
京都駅からは、市バスで『博物館・三十三間堂』のバス停前です。

あけましておめでとうございます。
お正月が終わると、次は十日えびすですね。
十日えびすとは、
ゑびすさんが1月10日の寅の刻つまり午前4時に生まれたということで、
誕生日を祝い、あやかろうとする庶民の願いで始まったとされています。
京都ゑびす神社は、東山区・大和大路四条をさがったところ、建仁寺の西側にあります。
十日ゑびす大祭には、1月8日〜12日の5日間でおよそ100万人が参拝されます。
実は、福笹は、江戸時代に京都ゑびす神社の宮司さんが考案されたものです。
お酒を飲んでから千鳥足で十日ゑびすにお参りする人が多いのは昔も今も同じで、
京都のお座敷では、お酒のことを「ささ」と言うことから、
「商売繁盛で笹もってこい」と、お酒を持って来た方に笹を授与したらオシャレやん
ということで始まったそうです。
また、ゑびすさんが右手に釣竿を持っていることをヒントに、
①笹は、松竹梅の竹の葉
②竹は節目正しく真っ直ぐ伸びる
③葉っぱの形が小判に似ているなどなどの理由で、商売繁盛に象徴となりました。
さて、京都ゑびす神社のお参りでは、本殿の正面からお参りした後、左に回って「横の戸を叩いてお参りすると願いが叶う」と、昔、誰かが言い出したそうで、江戸時代中頃には定着したそうです。
その横の戸には「優しくトントンと叩いてください。
えびす様のお肩を叩くお詣りです。ノックされるように優しくお願いいたします。」と書かれています。
これまで大勢の方が叩いたため、少し壁が曲がってしまっています。
十日えびすというと「儲かりまっか」の印象が強いですが、本来は家内安全と健康を願うものだそうです。えべっさんもニコニコしていて健康そう。
家内安全と健康があった上での商売繁盛ですね。
【アクセス】
京阪電車は、祇園四条駅から歩いて約6分。
阪急電車は、河原町駅から歩いて約8分。
バスは四条京阪前などの停留所が便利です。
【バックナンバーカレンダー】

