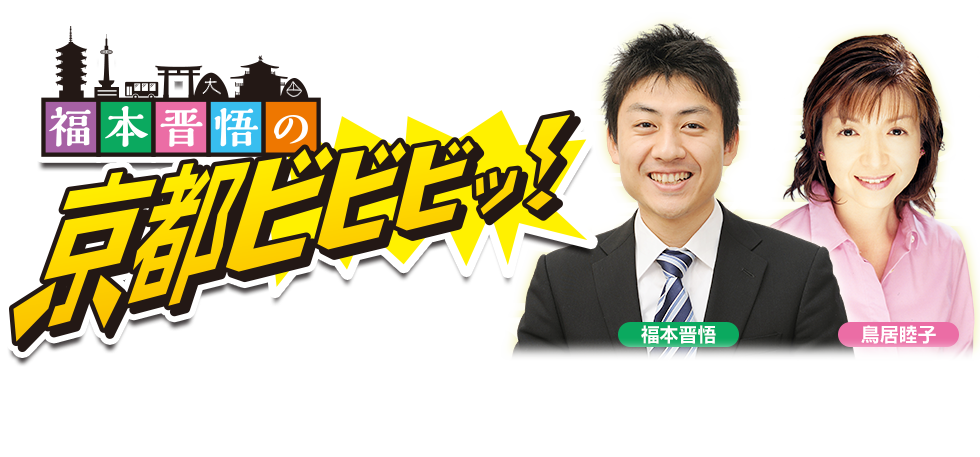
世界遺産・醍醐寺は、弘法大師の孫弟子である理源大師(りげんだいし)・聖宝(しょうぼう)によって、874年に建立されました。
聖宝の遺訓で、毎年2月23日に大法要が行われるようになりました。
その大法要を五大力尊仁王会(ごだいりき・そんにんのうえ)といい、「五大力さん」と呼ばれ親しまれています。五大力とは不動明王や金剛夜叉明王などの五大明王のことです。
五大力さんでは「餅上げ力奉納」という大きなお餅を持ち上げる行事があり、
例年テレビニュースで放送されるので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。
餅上げ力奉納は、五大明王の霊験を授かろうということから戦後まもなく始まりました。なぜお餅を持ち上げるかについては、①お供えとしてお米を奉納→②お米や餅米を奉納→③お餅を奉納→④大きなお餅を持ち上げる『力を奉納』と解釈されたのが理由だそうです。
上が赤、下が白色の大きなお餅と台座を何秒持ち上げられるかを競い、無病息災を祈ります。その重さは、男性は台座などを含め150キロ(5斗)、女性は90キロ(3斗5升)であるため、持ち上げられない人が多く、できても10秒くらいだそうです。
これまでの最高記録は、男性で15分4秒。11分11秒です。
なお、優勝すると、上の赤いお餅を。2位は下の白いお持ちの半分、3位は白いお餅の1/4を。また、参加者全員にお餅がもらえます。
引っ越しの時の大きなダンボールを抱えるように持ち上げるのがポイントです。
五大力さんの日にお参りして、ぜひあなたも力持ち(餅)に。
【アクセスなど】
醍醐寺さんの入山料は、大人600円、中高生300円。
醍醐寺の五大力さんは、2月23日朝9時から5時まで。
餅上げ力奉納は、小学生の部は10時から、女性の部は12時、男性の部は1時から。
エントリーはそれぞれ30分前で、例年男女とも約50人がエントリーされるそうです。
アクセスは、地下鉄東西線・醍醐駅から徒歩13分。

朱色の千本鳥居が山へ続く神秘さで、近年は外国人観光客に大人気の伏見稲荷大社。
外国人にとっては、京都駅から2駅というアクセスの良さや拝観無料も人気の秘訣です。
伏見稲荷で最も大切な行事が、初午大祭(はつうまたいさい)です。
711年の初午の日に、神様が稲荷山にご鎮座されたことから創建の日とされています。
毎年初午の日(2017年は2月12日)の朝8時から、神主さんがお供えをし、祝詞をあげ、巫女さんの神楽の舞などが行われます。
初午とは、2月の最初の午の日のことで、毎年変わります。
2月1日〜12日の間ですので、お稲荷さんの誕生日は毎年変わるといえるかもしれません。
昔の2月は春で今の3月の気候であり、人々が稲作を始める季節です。
山の神様が里に降りて来られ、田の神となられます。
稲荷は、「いねあり」「いねになる」という意味のある言葉で稲作の神様です。
これが後に、生活の神様、そして商売繁盛の神様へという意味も持つようになりました。
初午では「しるしの杉」が授与されます。
本来は、初午の日にだけに授与されるものでしたが、今ではお正月から授与されています。
イメージとしては福笹とか破魔矢のようなものです。
元々、平安時代中期になると、熊野詣が盛んになりました。
その行き帰りには必ずお稲荷さんにお参りするのが習わしになっていて、その時にはお稲荷さんにある杉の小枝をいただいて、体のどこかにつけ「お守りにする」のが一般的になり、これがしるしの杉のはじまりとされています。
奈良時代から現在まで、本当に多くの方がお参りをしている伏見稲荷。
千本鳥居は、実は1日に3本ほど、新しいものに立て直しているため、現在は平成に入ってからのものばかりです。
つまり、「伏見稲荷は、いつ行っても新しい」のです。
なお、伏見稲荷の鳥居は江戸時代以降参拝者から奉納されているもので、千本鳥居と同じ5号(柱の直径15センチ)で17万5000円からです。
【アクセス】
JR奈良線・稲荷駅すぐ。
京阪電車は、伏見稲荷駅が最寄りです。こちらは、土産物店が多いです。
上京区にある「千本ゑんま堂 引接寺(いんじょうじ)」の節分会(え)も注目です。
こちらの節分祭は、節分会といい、2日〜3日に行われます。
ゑんま堂には、ゑんま様が祀られています。ゑんま堂がある場所は、京都の三大墓地の1つがあった場所で、つまりこの世とあの世の境でもあるのです。
あの世へ行く前には、ゑんま様がいらっしゃるという訳です。なお、千本ゑんま堂は、一般的に呼ばれている名前で、正式には、引接寺といいます。
節分会では「ゑんま様のこんにゃく煮き」が、こぶ茶付きで400円で用意されています。
なぜ、こんにゃくなのか?その理由は、食べ物の中でこんにゃくには表も裏もありません。
「ゑんま様は嘘が大嫌いで表も裏もない素直なこんにゃくが好き」ということから、ゑんま様の大好物となったそうです。
また、千本ゑんま堂のこんにゃくは、ゑんま様の舌の形になっています。
ここにしかないオリジナルの器具を使って、手作りで舌の形になるよう作られているのです。
また、千本ゑんま堂は、狂言が演じられる場所としても有名で、3日夜7時30分から、鬼の演目の狂言を見る事ができます。
こちらの狂言はセリフがあるのが特徴です。
狂言が終わると、いよいよ豆まきです。おもしろいのは「福は内、鬼も内」なのです。
その理由は、この辺りは昔、盗賊などがよく出没していて、源為朝がゑんま様から授かった刀を薙(な)いだところ、鬼が改心したとか怪我をした所が治ったなどのいわれがあり、全国の追い出された鬼がここに来て、ゑんま様が悪い心をいい心に治した・・・という事で、「福は内、鬼も内」なのです。
千本ゑんま堂(引接寺)へのアクセスは、「乾隆校前(けんりゅうこうまえ)」のバス停が最寄りです。
京都の多くの神社仏閣で節分祭が行われますね。今回は、京都大学の近くにある吉田神社の節分祭をご紹介します。2日〜4日に行われます。
例年約50万人の参拝者が訪れ、露店が約800軒並ぶことでも有名です。
大注目は、数々の賞品が当たる「抽選券付き厄除福豆」が1袋200円で授与されていることです。
「厄除福豆」には抽選券が入っていて、特賞は、なんと車!
ほかにも10万円の旅行券、テレビなどの家電、お酒にいたるまで、約1000人の方が当選します。
当選番号は、4日火曜日午後1時からの厳正なる抽選で決まります。
当選発表は5日以降に境内に掲示され、ホームページにも掲載されます。
節分祭では、様々な祭事が行われますが、3日夜11時からは、火炉祭(かろさい)という古い御札を納める祭事が有名です。
吉田神社へのアクセスは、「京大正門前」のバス停から歩いて5分です。
【バックナンバーカレンダー】

