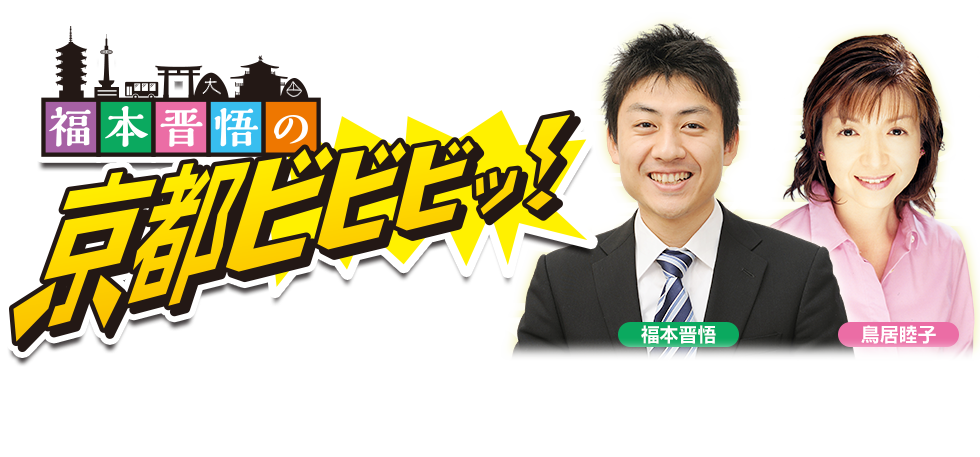

伏見区にある城南宮は、平安遷都の際に都の南の守護神として創建されました。そのため、方除(ほうよけ)という方角にまつわる災いを祓い除ける神社として有名です。
曲水(きょくすい)の宴(うたげ)は、遣水(やりみず)と呼ばれる小さな川のある庭でその流れの淵に出席者が座り、流れてくる盃が自分の前を通り過ぎるまでに詩歌を読み、盃の酒を飲んで次へ流し、別堂でその詩歌を披講するという行事です。
中国から伝わったとされ、日本では顕宗(けんぞう)天皇が(485年)宮廷の儀式として行われたと、日本書紀に書かれています。その後、特に奈良時代から平安時代中期までは宮中の年中行事として行われたり、藤原道長などの貴族が私的に行ったとする記録が残されています。
城南宮で曲水の宴が始まったのは、実は1970年(昭和45年)。大阪万博の年です。
万博で多くの人が関西に来るので、京都らしいものを城南宮でしようと考えられ、境内にある平安の庭で曲水の宴をすることになりました。2年後の1972年(昭和47年)には、毎年4月29日と11月3日の年2回開催することになりました。毎回、約2000人が曲水の宴をご覧になるそうです。
曲水の宴は、上賀茂神社や太宰府天満宮も有名ですが、日本で現在行われている曲水の宴は、いずれも昭和などに復元されたものです。
城南宮の曲水の宴は、午後2時から始まります。平安装束姿の歌人が7人、そのほかに歌を読み上げる朗詠者、琴を演奏する人が、平安の庭に登場すると、和歌の歌題(かだい)が発表されます。歌題は、毎回宮司さんが決めるので毎回違います。たとえば、源氏物語千年紀の年だと、源氏物語の話の1つである若紫(わかむらさき)が選ばれました。
平安の庭は、苔がきれいに生えていて、新緑の季節は木々の葉っぱが青々としています。その中に、山吹の黄色や桃の花のピンクの存在感があります。源氏物語に出てくる草木のオミナエシやリンドウなども植えられています。自然の香りがする素敵な空間です。
【アクセス】
京都駅八条口から、らくなんエクスプレスや市バスで。
車では、京都南インターチェンジからすぐです。
京野菜の春の味覚「京たけのこ」をご紹介します。
産地は、長岡京市や向日市などが有名ですね。
野菜を育てる場合、土は中性〜やや酸性がよいのですが、たけのこを育てるには強い酸性がよいそうです。たけのこづくりに適した場所は選ばれた場所といえるかもしれません。
たけのこは、たけのこ畑で育てられます。毎年、敷きわらやもみがらを蒔いたり、土入れという堆肥を入れる作業をします。これを繰り返すと、地層がミルフィーユみたいになっていきます。敷きわらを入れるのは、地表がふわふわしてやわらかい環境を作ることでたけのこを伸びやすくするためです。
このような作業をして大事に育てられた京のたけのこは、地表に出てくる前に収穫されます。たけのこ畑を熟知している農家の方が、長年の経験で「この竹からは、たけのこはここにある。」と、分かるそうです。
地面から顔を出す前に収穫される京たけのこは、白くてきれいです。そして、刺身として食べられるほど、灰汁がなくておいしいです。

浄土宗総本山の知恩院に横文字の行事があります。その名は、ミッドナイト念仏in御忌(ぎょき)。4月18日の夜8時〜19日朝7時まで行われます。
法然上人のお念仏を若い人にも触れて欲しいという思いで開催されているので、名前が横文字なんです。
御忌(ぎょき)とは御忌大会(ぎょきだいえ)のことで、法然上人の忌日法要を意味します。
御忌大会は4月18日〜25日に行われ、ミッドナイト念仏はその初日です。
元々、知恩院の方は、法然上人のお念仏を広める運動をされてきて、お母さん世代や若者にも仏教について肩肘張らず知ってもらう機会をつくりたいと活動されてきました。そんな中、1996年にミッドナイト念仏がスタートし、翌年97年には、御忌大会の初日に行うことになりました。
場所は、知恩院三門の楼上です。普段は入れない国宝の三門の中には150〜160人入れるスペースがあります。ミッドナイト念仏は夜8時に始まりますが、なんと入退場自由。好きな時間に参加できます。10分くらいで帰る人もいれば数時間いる人も。深夜に来る人や、リピーター、ちょっとお酒飲んでから来る人や、通りかかった人も来たり、外国人観光客が木魚叩いてみたり、大学生がツイッターで知って友達同士で訪れたりするそうです。深夜2時頃が1番大勢になるそうです。
一人ずつ木魚がありますので、お坊さんの様子を見て一緒に叩くのもよし、念仏を唱えるのもよし、皆さんの様子を見るのもよし。それぞれ好きな方法でお念仏の教えを体感できます。会場はロウソクの明かりに包まれ、木魚の音が外まで響き渡ります。
お坊さんにとっては正直体力の要ることですが、若い人に知って欲しいという思いでされています。
来場者は、始めて10年くらいまでは毎年200人未満。でもそこから増えて、今では800〜900人ほど来られています。
知恩院の方は、「昼間の御忌大会は厳かなものですが、ミッドナイト念仏は気軽にどうぞ」とおっしゃっていました。
何でもそうかもしれませんが、若い人に知ってもらうための方法を考えることが大切です。本筋だけは間違えないようにしたら、広める方法は時代に合わせるのがよいと取材して思いました。あの知恩院さんがこんなフランクな行事をされているって、本当に驚きです!
【アクセスなど】
ミッドナイト念仏in御忌は、4月18日夜8時〜19日朝7時まで。
場所は知恩院三門です。
アクセスは、阪急河原町駅から歩いて15分。地下鉄東山駅からは歩いて8分です。

お花見の季節ですね!京都には桜の名所が数多くありますが、今回は立命館大学衣笠キャンパスの近くにある平野神社をご紹介します。
平野神社は、京都で最初に咲く桜の木があることで有名で、ソメイヨシノをはじめ約60種。境内全域には約400本の桜があります。
早咲きや遅咲きの桜があるので、3月下旬からゴールデンウィークまで1か月以上桜が楽しめます。
京都市内で、同じ場所でこんなに長い間桜を楽しめるのは、平野神社くらいです。
平野神社は、平安遷都の時に桓武天皇によって、点在する4つの神様を集めて平城京から今の場所に移ってきた神社です。
平安時代後期、花山(かざん)天皇が平野神社の春祭りに来られて桜の木をお手植えされたことから、毎年お祭りの時に桜の木を植えていくようになりました。その後もしばらくは天皇が来られたときに植えるようになり、桜の木が多くなっていったそうです。
毎年4月10日には、桜花祭(おうかさい)が行われます。985年に平野臨時祭(りんじまつり)が開催されたのがはじまりで、大正時代になって地元の方が復活させたそうです。以来、毎年4月10日に桜花祭が開催されています。
10時に神前で祈祷し、11時には花山天皇陵に参拝。午後1時からは、神幸行列が平野神社を出発して金閣寺前まで行き、3時半頃に平野神社に戻ってきます。
平野神社で珍しいのは、花見茶屋という宴会ができるお店が4店舗あることです。屋台ではなく、4つのお店がそれぞれ境内のエリアを区切ってグループでの花見の宴会ができるようになっています。神社はお店にスペースを貸しているだけだそうで、大正時代から続いています。
江戸時代でも花見の宴会をやっていて、『平野の夜桜』が京都を代表する名所になりました。当時は、雪洞(ぼんぼり)にろうそくを立てて、ぼんやりとした明かりの中で夜桜を楽しんだそうです。情緒がありますね。
【アクセス】
衣笠校前のバス停を降りてすぐです。
【バックナンバーカレンダー】

