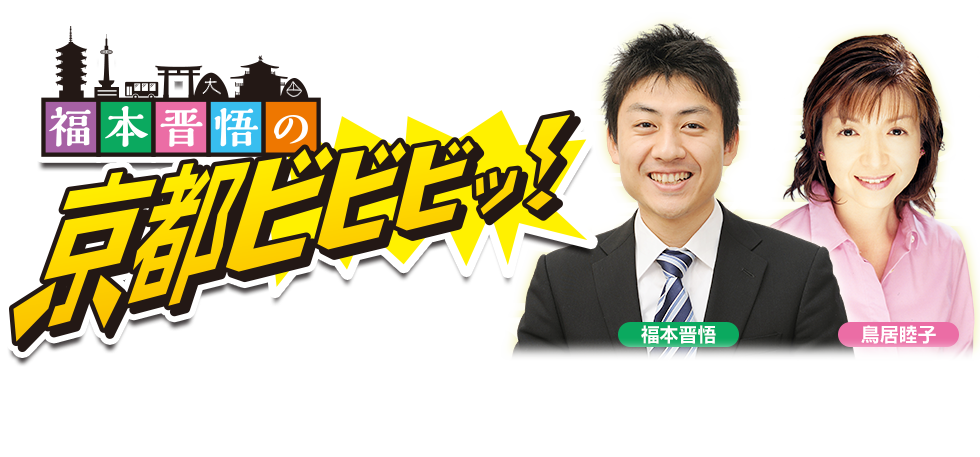
京野菜の特徴は、名前に発祥地名が入っていたり、形が珍しかったり、篤農家さんの活躍など様々で、鹿ケ谷(ししがたに)かぼちゃは特徴盛りだくさんです。
黄褐色でひょうたん型をしている鹿ケ谷かぼちゃは、京都市左京区の鹿ケ谷で栽培が始まりました。鹿ケ谷は銀閣の南の地域で、法然院のあたりです。
鹿ケ谷かぼちゃの歴史は、江戸時代の後半の文化年間に遡ります。現在の東山区いた玉屋藤四郎(たまや・とうしろう)という農家の方が、東北の津軽からカボチャの種を持ち帰り、隣村の鹿ヶ谷の農家に種を渡して作らせたのが、鹿ケ谷かぼちゃのはじまりとされています。
実は、鹿ケ谷で栽培し始めた頃は、普通の形のかぼちゃだったんですが、栽培しているうちに突然変異でひょうたん型になりまいた。大きさは、1キロ〜2キロあり、ほっておくと4キロくらいになることもあります。高さは20センチくらいあります。
江戸時代当時としてはかなり大きなかぼちゃですし、たくさん収穫できるので、京都でかぼちゃといえば、鹿ケ谷かぼちゃを指すほどになりました。明治時代に入り、鹿ケ谷かぼちゃは鹿ケ谷の名産となりましたが、大正時代に西洋かぼちゃが登場し、昭和に入ると作付面積が減少。昭和30年代には作られる量がわずかになりました。そのため、現在でも京都市内より、綾部市や南丹市で作られたものが市場に出回っています。
昭和に栽培量が減った理由として、好き嫌いが分かれやすい味だからだそうです。味が淡白で、サクサクしていてホクホク感や甘さが無いと。ということは逆に言うと、他のものの味に染まりやすいので、あんかけにして、だしを滲みさせて食べるのがおすすめです。鶏そぼろのあんかけが手軽にできそうです。
鹿ケ谷かぼちゃの特徴は、まだまだあります。ひょうたん型の上と下では、下に種があります。なので、上の方に実が多いです。なぜかは、分かっていません。
さらに、畑では濃い緑色をしていますが、収穫して完熟してくればお店に並ぶ時には、黄褐色になります。
ひょうたん型のカーブの部分を上手く使った料理がおしゃれです。鹿ケ谷かぼちゃは味が薄いので、小料理屋に来るお客さんは、「京都らしいなぁ」とおっしゃるかた方もいらっしゃるようです。さらに、ビタミンCが豊富です。種をとって空洞の部分にひき肉を詰める料理もあります。
旬の時期は7月中旬から8月中旬と短いですが、保存性が高いので、年内いっぱいまで食べることができるそうです。なので、江戸時代は保存食としての役割を果たしてきました。
鹿ケ谷かぼちゃは、デパートでは1500円から3000円で売られています。形がめずらしいので、観賞用の置物とされる方もいらっしゃいます。
このように、鹿ケ谷かぼちゃは、江戸時代に農業に熱心な方がいて、鹿ケ谷で栽培し、突然変異で形がひょうたん型になり、大きくて食べるところが多く、現代になってからは味が薄いのが「京都らしいわ〜」と言われたりとするなど、特徴盛りだくさんです。「京野菜の特徴のオールスター」と呼びたいと思います。
さて、毎年7月25日には鹿ケ谷にある安楽寺(あんらくじ)で「鹿ケ谷かぼちゃ供養」が行われます。鹿ケ谷かぼちゃを炊いて参拝者に振舞われる行事です。
江戸時代末期に、住職の真空益随(しんくう・えきずい)上人が本堂でご修行中、ご本尊阿弥陀如来から「夏の土用の頃に、当地の鹿ヶ谷カボチャを振る舞えば中風にならない」という霊告を受けられたことから始まった行事です。ぜひこの機会にお出かけください。

京都の7月といえば、祇園祭。平安時代から続く歴史のあるお祭りです。
2014年に祇園祭は、49年ぶりに前祭(さきまつり)と後祭(あとまつり)という本来の形に戻りました。これにより、前祭は23基による山鉾巡行が17日に、1週間後の24日に後祭の10基が巡行します。
祇園祭が本来の形に戻ることになったきっかけは、大船鉾(おおふねほこ)が150年ぶりに復活することでした。大船鉾は、四条烏丸西側の四条町の鉾で、名前のとおり大きい船の形をしています。全長7.47m、高さ6.35m、幅は3.25mあり、40人が乗れる大きな鉾です。
大船鉾は室町時代の1422年にできました。ご神体は三韓征伐を指揮した神功皇后(じんぐうこうごう)です。戦に勝って帰ってくる船ということで、昔から後祭の山鉾巡行の最後尾を巡行する「くじ取らず」の鉾です。
大船鉾は、応仁の乱で焼けてしまうなどしては復興してきましたが、幕末の蛤御門の変で焼けて巡行に参加できなくなり「休み鉾」となりました。
明治時代に復興を目指しましたが、当時京都では日本初の小学校を作っていて、学校の運営費はその地域が出すことになりました。その結果、四条町では大船鉾復活をしたくても難しくなり、いつしか「大船鉾のことは口にするな」という雰囲気になったそうです。
ただし、鉾の飾りである懸装品(けそうひん)を大切に保管され、ご神体と懸装品を飾る居祭(いまつり)を行うようになりました。1995年には居祭も中止になりましたが、翌年にはお囃子を復活させようと笛や太鼓は買ったり、岩戸山(いわとやま)のお囃子の方に教えてもらうなどされてきました。そして、いよいよ鉾が完成し、2014年の復活を迎えました。
後祭の山鉾巡行は、前祭とは逆ルートで烏丸御池がスタートです。御池通から河原町通を経て、四条烏丸に向かいます。
3年前に新たな船出をした大船鉾。今年もその勇壮な姿をしっかりと目に焼き付けたいですね。

向日市はタケノコや向日町競輪で有名ですが、2009年7月に『京都激辛商店街』が誕生しました。激辛商店街といってもその名前の商店街があるわけではなく、阪急の東向日駅や西向日駅、JRの向日町駅などを中心に市内の広い範囲に激辛料理を出すお店などがあることを意味しています。
向日市で激辛商店街が始まった経緯は、町おこしです。向日市を愛する有志たちが、タケノコの産地としての特色を生かすために、竹馬全国大会を開いたり、金沢まで270キロを竹馬で歩いたりされたんですが、マニアックすぎて町おこしというほどの効果は出ませんでした。そこでリーダーは考えました。他に何か無いかなぁ・・・「ないものは無い!無かったら作ったらいいやん!」と。考えた結果、『激辛』にたどり着きました。
そもそも激辛は人気がありますし、食べると元気が出たり、癖になりますよね。そんな魅力のある激辛で、観光客に来ていただこうと考えたわけです。なので、向日市と激辛の関係はありません。
激辛商店街の効果は絶大でした。向日市の観光客は、2008年は年間3000人でしたが、激辛商店街が始まった2009年には、約6万人に急増!20倍になりました。
激辛料理は、ただ辛いだけじゃなくて、辛くて旨い、つまりカラウマであることが大事です。激辛商店街が始まった当初は、「食べ物を粗末にしてはいけない」という意見がきたそうです。辛すぎて食べられず、残す人もいるからです。なので、辛さレベルを設定して、クリアしないと次のレベルにチャレンジできないなどのルールを作るなどされました。
また、2012年には、辛くて旨いカラウマナンバー1を決める『KARA−1グランプリ』がスタートしました。年1回開催で、今年も開催予定です。
東向日駅前のお店で、辛いパスタをいただきましたが、辛いものはおいしいですね!最初は意外に大丈夫と思っていても、食べるにつれて汗をかいてきて、辛くなってきて、唇がヒリヒリしてきて「かっら〜」と言いながら水飲んで、また食べる。食べていたら元気になりました。
激辛商店街やKARA-1グランプリは、激辛と向日市を愛する人との「カラミ」で成功している町おこしなのです。
京野菜のもう1つのナスは「京山科なす」で、山科なすを改良しブランド化されました。
名前のとおり、元々山科エリアで栽培されていました。
実は、明治末期から昭和初期は、京都市内のナスの6〜7割が山科なすでした。その後、昭和20年頃から、千両なすが登場し、京都の大手種苗会社が昭和30年後半から種を売り出しました。千両なすは栽培や収穫に優れたナスなので、山科なすの生産が減っていきました。
そんな状況が続いていましたが、京都府では平成9年から山科なすの復活を目指して収穫量アップなどの取り組みをし、翌年ブランド認証されました。
山科なすは、皮が薄く、乾燥に弱いので袋づめにして売られます。現在では、木津川市が生産の中心ですが、もちろん京都市などでも作られています。
【バックナンバーカレンダー】

