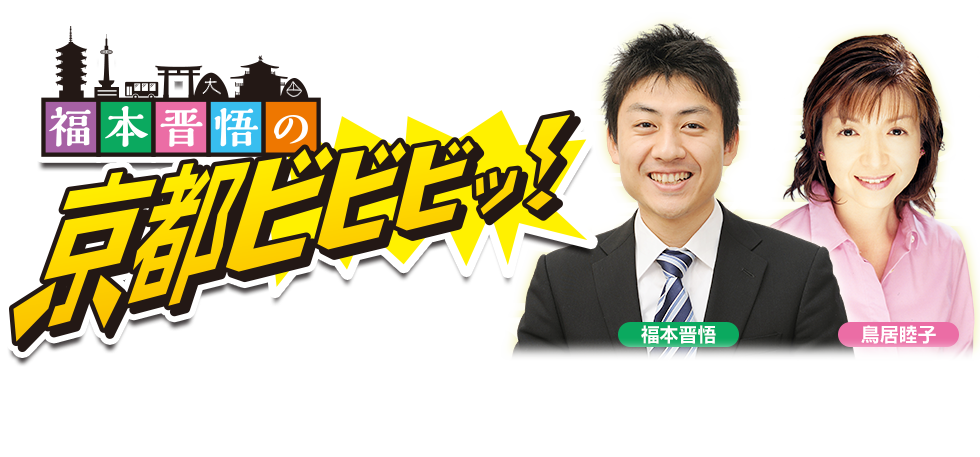

京の台所・錦市場。四条通から一本北の錦小路通にある錦市場は、東西390メートルあり、約130店舗が商店街振興組合に加盟しています。
錦市場の道幅は3.2 mから 5mと狭く、歩いていると、魚やだし巻きを焼いた香りがしてきます。漬物、京野菜、魚、お菓子、お土産など様々なお店が軒を連ねているので、京都のものはここで全て揃うといっても過言ではないでしょう。
修学旅行生の人気のスポットであり、近年は外国人観光客が多く、調査をされたところ、なんと6割が外国人だそうです。
錦小路の魚市場としての歴史は古く、平安時代になる頃に開かれ、御所へ新鮮な魚を納めていたといわれています。江戸時代になり、幕府から錦市場に魚問屋の称号を与えられ、京都の特権的鮮魚市場として歩み出したのが1615年です。
名前の由来は諸説あります。その1つは、かつて具足小路(ぐそくこうじ)と言われていたという説で、具足とは鎧兜のことで、平安時代にこのあたりで馬具を売っていたとか、御所に出入りする前に具足を付け外ししていた場所だったという説です。
他には、四条通の南側に綾小路(あやのこうじ)があり、美しい着物を綾錦ということから、平安時代の後冷泉天皇が「錦小路」と改めたという説。錦織を売っていた場所だからという説などがあります。
さて、錦市場専用のイートインスペース『京町家錦上ル』をご存知でしょうか。
錦通麩屋町(ふやちょう)から歩いて1分くらい上ったところにある町家で、ワンドリンクもしくは一品を注文するだけで、錦市場で買ったものを食べることができる場所です。
おばんざいは、温め、切り分け、盛り付けをしてくださいます。京都の地酒と一緒にいかがですか?
イートインスペースの利用は、11時〜5時半。お休みは月曜です。
夜は、錦市場から仕入れた食材を使っている京料理をいただけるレストランの営業をされています。
食べることは観光の大きな魅力です。京都のええもんは料亭などでしか食べられないかと思いきや、実は、ええもんを錦市場ですぐに食べることができます。
【アクセスなど】
錦市場は、地下鉄・四条駅や阪急・烏丸駅が便利です。
夕方5〜6時には閉まる店が多いのでご注意ください。

文化財特別公開キャンペーンである『京の夏の旅』が、9月30日まで開催中です。
特別公開されている大雲院は祇園にあり、創建時からずっと非公開の浄土宗のお寺で、檀家さん以外はなかなか参拝することはできません。
大雲院は、織田信長・信忠親子の菩提寺として烏丸御池(今の京都国際マンガミュージアムの場所)に創建されましたが、3年後には秀吉の都市政策で四条寺町に移り、昭和48年に祇園の今の場所に移転しました。
ちなみに、本堂にある織田信忠の木像は、フィギュアスケートの織田信成さんに本当にそっくりです!十数メートル離れた場所からの見物ですが、特に唇の分厚さや耳と鼻の形が似ています。
大雲院の境内にある登録有形文化財・祇園閣は、大倉財閥の創始者・大倉喜八郎さんが、自身の90歳の記念として、昭和天皇の即位記念として、京都の名所をつくりたいという3つの思いから、昭和3年に建立されました。また、「祇園祭のすばらしい眺めをいつも披露したい」と考え、山鉾のような形になっています。
大雲院は、鉄筋コンクリート造りの3層建てで高さは36メートル。八坂の塔より高く、小高いところにあるため、京都ホテルオークラの最上階と同じくらいの高さだそうです。そこからは、祇園の町並みを高いところから見られます。祇園の街は瓦屋根が本当に多いと気づきました。遠くは、京都タワーや八幡の男山まで見えます。
また、創建400年の昭和63年には、祇園閣の内部の壁面をペンキで中国・敦煌の壁画の模写にしました。他には、千手観音図などが描かれています。
祇園閣の屋根は銅版葺きで、1階の入口の扉も銅です。そのため、一般の方から「銅閣」と呼ばれることもあるそうです。
祇園閣の内部や眺めは写真撮影禁止ですので、ぜひこの機会にじっくりとご覧ください。
銅閣とも言われている祇園閣は、金閣、銀閣と『同格』に魅力的です。
【アクセスなど】
大雲院は、円山音楽堂や八坂神社、高台寺からすぐのところにあります。
「東山安井」のバス停から歩いて約5分です。
拝観料は、大人 600円です。受付時間は朝10時から4時までです。

まだまだ暑い日が続きますが、これから秋の紅葉シーズンに向けて京都を観光する人が増えていきます。
今回は、休憩やお土産としておすすめの祇園にある和スイーツ人気店「ぎおん徳屋」の本わらび餅をご紹介します。
ぎおん徳屋の本わらび餅は、高級割烹料亭のコース料理の最後に出てくるデザートだけを出すようなお店をできないかというわらび餅好きのオーナーの発想から始まりました。
知り合いの料理人3人からわらび餅の作り方を教えてもらい、「いいとこ取り」をして完成させたそうです。
巷にはわらび粉をあまり使用していないわらび餅がありますが、ぎおん徳屋では、上質の国産の本わらび粉100%使用しています。
とろけるような口あたりですが、弾力があり、初めて食べる食感・・・美味しい!
お店で食べると1200円です。
なお、「おもたせ」ですと、並ばなくても買えます。「おもたせ」は数に限りがありますが、予約しておくこともできます。
わらび餅3個入×4個、きな粉4袋付きで2500円です。
【アクセスなど】
・場所は、祇園の花見小路です。
・営業時間は12時〜18時。
お店が比較的空いているのは、開店直後や17時を過ぎてからだそうです。
9月9日は、五節句のひとつ「重陽の節句」です。
五節句とは、江戸時代に定められた5つの式日(今でいう祝日)をいい、1月7日の人日の節句(七草粥)、3月3日の上巳の節句(桃の節句/雛祭り)、5月5日の端午の節句、7月7日の七夕の節句、9月9日の重陽の節句があります。
古来より、奇数は縁起の良い陽数と考えられ、その奇数が連なる日をお祝いしてきました。中でも一番大きな陽数である9が重なる9月9日を「重陽」といいます。
重陽の節句は、日本では平安時代初期に貴族の宮中行事として取り入れられました。当時は、中国から伝来したばかりの菊を眺めながら宴を催し、菊を用いて厄祓いや長寿祈願をしました。これが時代とともに民間にも広がり、江戸時代に五節句の1つとなって親しまれるようになり、五節句を締めくくる行事として、昔は最も盛んだったといわれています。
京都でも色々な神社で、重陽の節句の行事がされていますが、市比賣(いちひめ)神社の重陽祭では、長寿を祈るため菊酒がふるまわれます。 菊といえば晩秋の花という印象ですが、旧暦の9月9日は今の10月中頃にあたり、まさに菊の美しい季節でしたが、新暦では季節感が合わなくなってしまいました。
さて、市比賣神社では同じ日にカード感謝祭が行われます。
市比賣神社は、平安京唯一の官営市場に中に建てられた守護所で、かつては堀川七条のあたりにありましたが、安土・桃山時代に現在の地に移りました。
平安時代当時、商いの御免状「鑑札(かんさつ)」を発行していて、これは今でいうとカードです。宮司さんが「カードに感謝したり、大事なものとして理解することが大切」と考え、「カードを守るお守り」をカード型にして出されることになりました。
その後、「使わなくなったカードを神社でどうにかしかしてくれへんか?」と相談があり、期限切れ・使用済みの病院の診察券や会員証などのカードを感謝して納め、カードによる様々な災いから身を守っていただこうということで、カード感謝祭を始められました。
なお、カード感謝祭の時以外は、境内にガラスの壷があり、そこに収めることができます。
【アクセス】
京都市下京区の河原町五条下ルです。
「河原町正面」のバス停から歩いて3分。
京阪・清水五条駅から歩いて5分です。
参拝時間は、朝9時〜夕方4時半までです。
【バックナンバーカレンダー】

