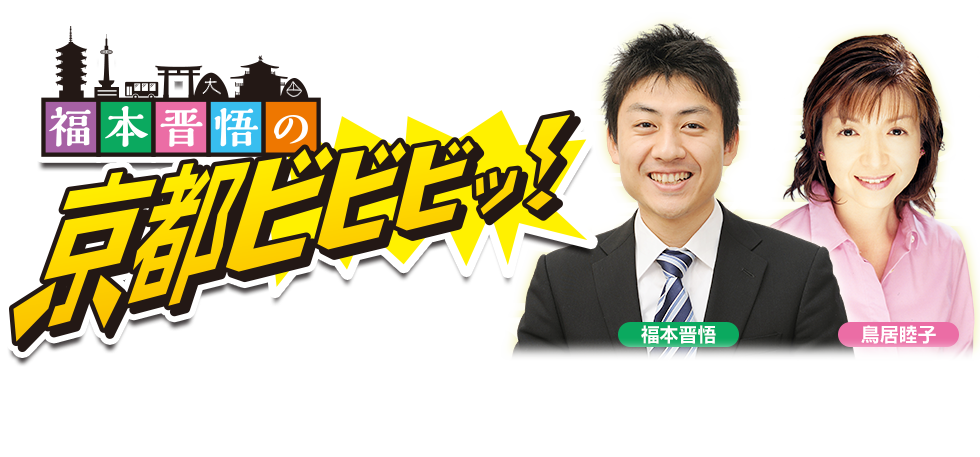
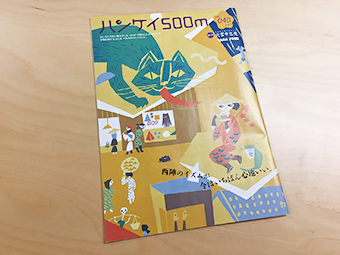
こだわりの強い「京おんな」を満足させるフリーマガジン「ハンケイ500m」が、11月10日発行で40号を迎えました!
奇数月発行で実部数3万部。地下鉄の駅などで入手できます。
「ハンケイ500m」の特徴は、京都市営バスのバス停から半径500mに限定した京都の「本物」を支えてきた職人さんの人物紹介です。お店の人のことを知ってから、食べたり、買ったりしたい人にオススメです。
生まれも育ちも京都の編集長・円城新子(えんじょうしんこ)さんによりますと、「京都はバス停が約1500か所と多い。半径500mは狭そうに思えますが、探してみると選ぶのに困るほどおもしろい方がいらっしゃいます」とのことです。
フリーマガジンを始めるにあたり色々考えた結果、本物志向で、こだわりの強い「京都の地元の人向け」にされました。
「ハンケイ500m」最新40号は、「大宮中立売」のバス停特集です。
ホームページでも読むことができます。
自ら歩いて、人に出会い、記事を書くという取材を続けていらっしゃるハンケイ500m。
私も京都の取材を続ける一人として、刺激をいただきました。
前回の聖護院かぶに続いて、同じく11月中旬からが旬の聖護院だいこんをご紹介します。
聖護院だいこんの食べ方は、やっぱりおでんや煮炊きですよね!
有名な行事は、12月7日〜8日の千本釈迦堂の大根(だいこ)炊きで、こちらでは聖護院だいこんが使われています。
聖護院だいこんの歴史は、尾張から左京区の金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)に奉納された大根から始まります。2本の長大根が奉納されたと知った篤農家・田中屋喜兵衛(たなかやきへい)さんが、その大根の種を分けてもらったそうです。
尾張から運ばれてきた大根は宮重(みやしげ)大根といい、ごぼうのように長く40センチくらいあったそうです。
田中屋喜兵衛さんは、早速その種を撒いたところ、長い大根ではなく丸い大根ができました。その理由は、聖護院かぶと同じで土が浅いことです。できた丸い大根は、長い物と比べて密度が高く、大きさのわりには重く、身がしっかりしていて、炊いても煮崩れしにくい大根となりました。
昭和初期の写真などを見ると、聖護院だいこんはまだ微妙に長かったり平たかったりしているのですが、いいものができた時の種を保存・研究して、今は安定して丸い大根ができるようになりました。
研究熱心な方々のおかげでできた聖護院かぶと聖護院だいこん。聖護院へのお参りもお忘れなく。
今日は、11月中旬からが旬の聖護院かぶについてです。
聖護院かぶは、その多くが千枚漬けに使われていて、サラダやかぶら蒸しにもされます。
聖護院かぶの歴史は、江戸時代からです。大津の堅田に“いいかぶ”があると聞いた聖護院村の篤農家・伊勢屋利八(いせやりはち)さんが、かぶを持ち帰り聖護院で栽培すると、おいしいかぶができました。最初は平たい形のかぶでしたが、栽培していくにつれてだんだんと丸くなり、ボールのようなかぶになったんだそうです。
その理由は、聖護院エリアの土です。長い物ができない状態、つまり土の部分が浅いことが理由です。土の下には粘土層があり、この粘土層が浅い部分にあるため、土を深く耕すことができないのです。太古の昔、京都の地形ができる時、土は川などで南に流れてしまい京都市内でも北の方にある聖護院の土は浅くなっています。つまり、土の部分が浅いために作物は地中で縦に伸びることが難しく、横に広がるようになり自然と丸くなったのです。一方で、京都の南の方は土が深いので、九条ねぎなどの栽培に適しています。
江戸時代当時は、年によって、いい丸形にならなかったり、おいしくなかったりした訳ですが、研究熱心な伊勢屋利八さん達は、いい品種ができるように、丸くておいしい年の種をちゃんと記録・保存し、翌年にその種を使って水のやり方などを色々工夫していきました。すでにこの時代には、「種は財産」という意識があったのです。
千枚漬けにするには2キロぐらいがよく、年末に間に合うように収穫されています。ただ、気温の変化で収穫時期がずれることもあるので、その場合は、種を蒔きなおすなどして、お歳暮のタイミングに合わせるようにしているんだそうです。

1998年11月に京都市学校歴史博物館が誕生しました。私立学校がその学校をテーマとした博物館は数多くありますが、様々な学校の歴史を扱った博物館は日本で唯一です。
日本で最初の学区制の小学校は京都にできました。学制ができたのは明治5年ですが、それより早く、明治2年の半年間に小学校64校が作られました。蛤御門の変の後、復興政策の1つとされたのが教育で、町衆がお金を出し合って小学校をつくったのです。
京都の町の碁盤の目をいくつか合わせた自治組織を町組(ちょうぐみ)と呼びます。明治になり、町組をどれも同じような規模になるように再編されました。これを「番組」といい、番組単位で小学校を作ったので『番組小学校』と呼ばれるようになりました。
おおよそ家1000戸で1つの小学校くらいだったそうで、たとえば四条河原町から四条烏丸、五条烏丸から五条河原町のエリアで3つの小学校ができました。
ちなみに、上京第1番組小学校は、西陣にある現在の乾隆(けんりゅう)小学校で、北西から東方向へ番号がふられていきました。
番組小学校には、消防署や交番、公民館もありました。京都の町には「火消し」がなく、蛤御門の変で町が焼けたので、町衆から「火の見やぐらが欲しい」という声があり、「ならば小学校の場所に消防署や交番も公民館もまとめよう」となったんだそうです。
戦後、少子化などで統廃合や閉校となった小学校の多くは、地域の施設になっています。地域の人がお金を出して作った小学校の建物を壊すことはできないからです。下京第11番組小学校で、元・開智小学校は、京都市学校歴史博物館になりました。
常設展をご紹介しましょう。大正時代の自由教育のコーナーには、新聞を使った国語の授業風景の写真があります。黒板には、「カタイコト・・・外交、政治、軍事、産業。」「記事と論説がある」など、新聞の構成を教えています。
教科書コーナーも興味深いです。明治初期は寺子屋のような内容ですが、その後、西洋風に行き過ぎます。戦時中は戦争の内容に染まります。そして、戦後は墨塗り教科書です。
おもしろいのは、昭和5年の「京都小学唱歌」という音楽の教科書の『唱歌の心得』です。「気をつけと同じような姿勢ですが、あまり固くならないで、のんびりとして、両足でしっかりと立ち、ゆったりとした気分で歌いなさい。」「大声を張り上げて歌うのはよろしくありません。」「唱歌の前には、必ず鼻汁をかんでおきなさい。」などなどの心得には、つい笑ってしまいました。
学校でこどもに何を教えるのかを考えることはとても大事ですね。また、学校ってありがたいものだなぁとつくづく感じました。
【アクセスなど】
場所は下京区御幸町通仏光寺で、四条河原町から南西に歩いて10分くらいです。
河原町松原のバス停からは、歩いて約5分です。
開館時間は、朝9時〜夕方5時まで。お休みは水曜日。
入館料は大人200円、小中高生は100円です。
【バックナンバーカレンダー】

