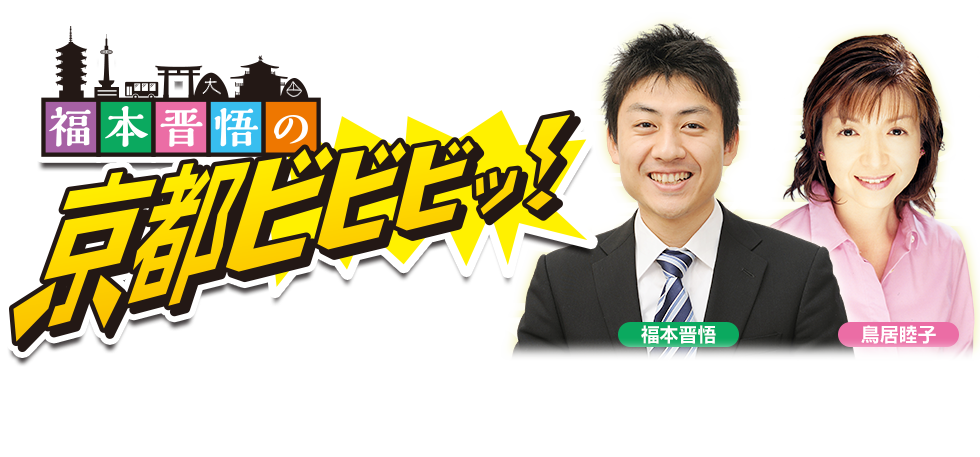

四条烏丸から歩いて5分、烏丸御池からは3分のところに六角堂はあります。
本堂を上から見ると六角形なので、一般には「六角堂」と呼ばれています。高層ビルに囲まれたところにあるお寺で、いつもお線香の香りがしているオフィス街とは別世界のようなお寺です。
六角堂の正式名称は、頂法寺(ちょうほうじ)。西暦587年、聖徳太子が建てました。
この時、聖徳太子は大阪の四天王寺建立のための資材を求め、山城の地に来られました。
そんなある日、聖徳太子が泉で沐浴をされると、その夜、夢に仏様が現れ、「この地に留まりたい」いうお告げを見られました。そこで聖徳太子は、ここにお堂を建てようと決心しました。それが六角堂です。
仏教での最高の形は、円形です。終わりが無く、回る。つまり「教えが続いていく」という意味です。ただ、円形の建物を建てるのは、その当時難しかったので、それに近い形で六角形になりました。
さらに、6つの感覚、「見る、聞く、嗅ぐ、食べる、触れる、心で感じる」これらが正しく機能していれば、欲が邪魔することなく生きていけるという意味もあります。
六角堂と呼ばれるようになったのは、平安時代からだそうです。町の人々が呼び始め、「六角さん」とも呼ばれています。町の集会場としての役割もありましたし、祇園祭の山鉾巡行のくじ取り式は、昔は六角堂で行われていました。
火災で本堂が焼けてしまったときは、六角形ではなく四角のときもあったそうです。今の本堂は、明治10年に建てられました。
六角堂は、いけばな発祥の地としても知られています。聖徳太子が沐浴されたと伝えられる池の跡があり、初代住職は隋から帰ってきた小野妹子です。如意輪観音の守護を聖徳太子から託された小野妹子は、坊を建て朝夕に仏前に花を供えたことが、池坊流の起こりになったとされています。
本堂東側には、有名な「へそ石」があります。平面六角形の平らな石で、旧本堂の礎石と伝わります。六角堂が平安京の前から存在し、位置もほぼ移動していないことから、この石が京都の中心であると言われています。
地理的に京都の中心であり、人が集まるという意味でも中心地と言えますね。いつ頃からへそ石と呼ばれるようになったのかは定かではなく、六角堂がそう呼んでいるわけでもないとのことです。
なお、平安京を建設する際に通り(六角通)を作ろうとしたら、そこに六角堂があったため、桓武天皇の勅使が六角堂に行くと、黒い雲に覆われ・・・六角堂がひとりでに5丈(約15メートル)移動したというエピソードが残っています。
六角堂は縁結びのスポットとしても有名です。逸話としては、平安時代初めに嵯峨天皇の夢枕に「六角堂の柳の下を見よ」とのお告げがあり行ってみると、そこには絶世の美女がいて、お妃に迎えました。
それから六角堂の柳に願をかけると良縁に恵まれるという噂は広まり、この柳は「縁結びの柳」として人々に親しまれています。 柳の2本の枝におみくじを結びつけると良縁に恵まれるということで、1本ではなく、2本の枝とおみくじを一緒に結びます。
さて、鐘の音を聴くと「お寺やなぁ」と思いますね。実は、六角堂の鐘は、昔は法要の時以外は、大火事や鴨川の氾濫などの災害を知らせる時にしか鳴らさない鐘でした。
鐘は門を出て、六角通を渡ったところにあり、太平洋戦争後、六角堂の鐘の隣にあるお花屋さん「花市」のご主人が代々、管理をされています。戦後は、朝6時、正午、夕方5時にご主人が鐘を鳴らしていましたが、先代のご主人の時に、調子が悪いときには難しいということで、導入されたのが、「全自動撞木」つまり全自動で鳴る鐘です!
人がいないのにいきなり鐘が鳴るんです。お昼12時と夕方5時が自動で、朝6時は、花市さんのご主人が今も鳴らされています。
これ以外にも人の手で鐘が突かれる日もあります。広島と長崎の原爆投下の日、終戦記念日、五山の送り火の日に、鎮魂と供養のためにされます。一般公開されるのは年に1度だけで、除夜の鐘です。
六角堂は、聖徳太子の時代から京都のみなさんと共に時を刻んできたお寺と言えます。烏丸にお出かけになるときは、立ち寄ってみてはいかがでしょうか?
【アクセスなど】
・六角堂は中京区の烏丸六角にあります。
・地下鉄・四条駅や阪急・烏丸駅から歩いて5分。地下鉄・烏丸御池駅から歩いて3分です。
・拝観時間は、朝6時〜夕方5時までです。
11~12月が旬の堀川ごぼうを紹介します。
歴史は安土桃山時代にタイムスリップします。豊臣秀吉が京都に聚楽第(じゅらくだい)を建て、周りに堀をめぐらしました。しかし、その後、聚楽第は取り壊され、お堀は周辺住民のごみ捨て場になってしまいました。
そこに捨てられたごぼうから根や芽が出て再び成長、1年後にはかなり大きなごぼうになり、長さ50センチ、太さ6〜9センチのれんこんくらいの太さになったそうです。
そして、そのごぼうを炊いて食べた人がいたのです。すごくやわらかく、真ん中に穴があいていて珍しく、農家の人たちが作り始めたというのが起源です。
普通のごぼうを寝かせたら、1年後には元々のごぼうの部分が太くなったのです。つまり、堀川ごぼうは、品種改良をしたわけではなく、普通のごぼうの栽培方法を変えてできた京野菜なのです。
堀川ごぼうは、どちらかというと料亭などの料理屋さん向けです。肉入りれんこんのように、空洞部に肉を詰めて煮る「鋳込み」料理が有名で、味がしみ込みやすいのが特徴です。
やまのいもはヤマトイモの一種で、11月〜2月の冬野菜です。
とろろ汁で食べるのが一般的ですが、京都では高級和菓子にも使われます。上用まんじゅうや紅白饅頭の薄皮の部分に使うとふっくらします。その他、そばの「つなぎ」にも使われています。
産地の1つである南丹市や亀岡市へは、兵庫の丹波地方から江戸時代の終わり頃から明治時代の初め頃に入ってきたといわれています。
もう1つの産地の宮津市では、明治の初め頃から栽培されています。
宮津の栽培の特徴は、ヤマノイモとショウガの混植です。北から南へ植えていく場合、東側の列にやまのいもを、西側にショウガを植えていきます。そうすることで、いものつるでショウガに陰を与え、一方で、ショウガの葉でやまのいもの株の乾燥を防ぐ効果があります。宮津の農家さんの工夫ですね。

今年の紅葉シーズンもわずかです。銀閣寺と哲学の道の散策はいかがでしょうか。
足利8代将軍・義政が建立した銀閣。わび・さびの雰囲気が漂います。
庭の苔を写真に撮っている人が多く、その時、庭の通路以外はほとんど苔の緑色だということに気づきました。苔が多い理由は、義政が、銀閣寺の庭を西芳寺(さいほうじ。通称:苔寺)と同じように造ることを理想としていたからだそうです。
庭には他に、砂で波紋を表現した銀沙灘(ぎんしゃだん)があり、苔の緑、銀沙灘の銀、紅葉の赤の中に銀閣が美しく映えています。
さて、哲学の道は、北は銀閣寺あたりから南は永観堂の近くまでの約2キロの道です。
この道は、明治時代に文人が多く住むようになったため「文人の道」と呼ばれ、その後、哲学者の西田幾多郎らが散策したため「哲学の小径」と言われたり、「散策の道」「思索の道」などと呼ばれていました。
そして、1972(昭和47)年に地元住民が保存運動を進めるに際し、相談した結果「哲学の道」と決まり定着しました。
春は桜、秋は紅葉の名所で、多くの方が散歩しながら観賞されます。哲学の道沿いにはお土産屋さんや喫茶店が多く、いくつかのお店を訪れましたが、質問すると色々教えてくださるお店が多いように感じました。
哲学の道を歩いている人は多いので、人が写らない写真を撮りたければ早朝がチャンスです。
哲学の道の南の終点に着いたら、帰りは白川通と丸太町通の交差点「東天王町」のバス停から四条河原町や京都駅へ向かうのが便利です。
紅葉を眺めて散歩しながら、思索に耽てみるのはいかがですか?
【アクセスなど】
銀閣寺の拝観料は大人500円。
「銀閣寺前」もしくは「銀閣寺道」のバス停が便利です。
【バックナンバーカレンダー】

