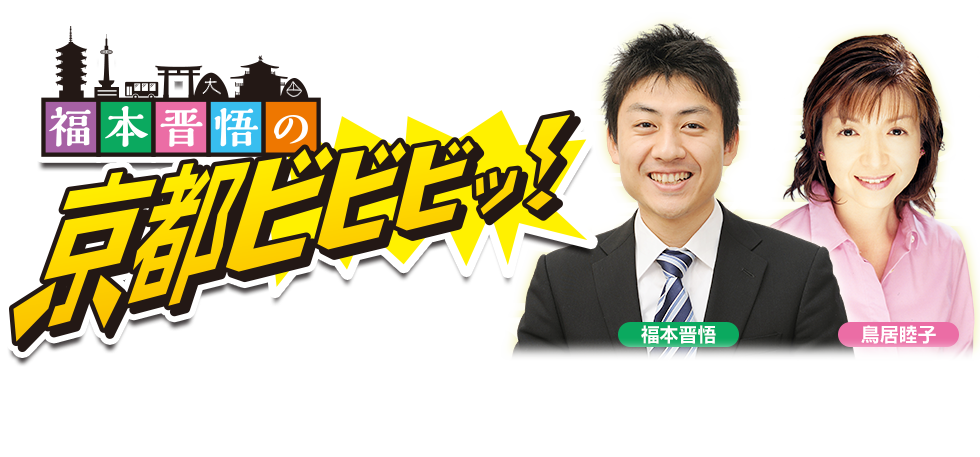
大手印刷会社・大日本印刷(DNP)の京都工場は、太秦にあります。
京都工場の敷地内に2014年10月、「DNP京都太秦文化遺産ギャラリー」をオープンされました。
「有形・無形の文化財をどう保存するか」。DNPは、美術館・博物館の収蔵品を『デジタルアーカイブ』にする仕事を1980年代からされてきました。
具体的には、貴重な美術品などをスチールカメラで撮影し、コンピューター上で見られるようにすることです。一箇所を拡大して見たり、立体の作品でしたら上や下から見られます。2006年には、パリのルーブル美術館のスペイン絵画の展示館でDNPの機械が導入されました。
さらに、「京都でも」ということで、『京都・文化遺産アーカイブプロジェクト』がスタートしました。京都が誇る有形・無形の文化遺産を壊すことなく保存・継承していくことを目指して、発足したプロジェクトです。
お寺にある貴重な襖絵などを多くの人に見て欲しいけれど、公開し続けると劣化してしまいます。ならばアーカイブをつくろうということで、8000万画素のカメラやスキャナーを使って、高精細映像で文化財を撮影。お寺や神社などの貴重な文化遺産を収録・保存されています。
さらにさらに、記録・保存・公開をするための複製事業「高精細複製『伝匠美』」をされています。
例えば、知恩院の大方丈にある襖絵は、金箔を使った狩野派の作品です。これを4面実物大で再現され、ギャラリー展示されています。襖の上に金箔を張って、その上に高精細印刷をされます。金箔の上にきれいに印刷する技術は難しく特許だそうです。印刷されたものは、元の作品の汚れなども忠実に再現されています。
DNP京都太秦文化遺産ギャラリーでは、昔と今の最先端のワザを見られます。また、保存が大変な文化遺産をどうにかしたいという印刷会社の思いと挑戦を感じました。
【アクセスなど】
天神川御池の交差点を上がったところです。
地下鉄東西線・太秦天神川駅や嵐電天神川から歩いて3分です。
開館時間は11時から夜7時まで(土曜日は6時まで)。
お休みは日曜と祝日で、入場は無料です。
京こかぶは京野菜ですが、1970(昭和45)年にできたので、京の伝統野菜ではありません。(明治以前に導入されたものが京の伝統野菜と定義されています)
京都市右京区京北地域(旧京北町)でつくられていた評判のよいこかぶを「京こかぶ」と名づけ、ブランド化しました。したがって、京こかぶは、品種名や独特の栽培方法でできたものではありません。旧京北町は、山間地域で寒暖の差が大きく、夏の涼しい気候を活かしてこかぶの栽培をはじめました。
特徴は少し大きいことです。こかぶはピンポン玉くらいですが、京こかぶは直径6〜7センチのものもあります。
出荷にも特徴があります。たとえば聖護院かぶは出荷のときに葉っぱを切りますが、京こかぶは、葉のついた状態で出荷します。
有名な料理は、かぶら蒸しや漬物ですが、葉っぱも食べられるので、葉っぱを炒めてチャーハンに使えます。さらに、生でも食べられるので、スライスしてマヨネーズつけたり、サラダにするのも美味しいです。

寒い冬は、熱いお風呂が気持ちいいですね。
京都にはいくつもの温泉や銭湯がありますが、今回は大正12年創業の船岡温泉をご紹介します。
「温泉」と言ってもいわゆる銭湯なんですが、ちゃんと許可をとって温泉と名乗っています。それは、昭和8年に日本で初めて電気風呂を導入し、「船岡特殊温泉」として温泉の許可を受けたからです。
船岡温泉の建物は、登録有形文化財になった唐破風造です。脱衣所の天井には、鞍馬天狗と牛若丸の彫刻があったりするなど、芸術的なスポットとして近年は外国人にも人気です。
お風呂に関心のある外国人が1日に何十人と来られるそうで、私がいた時は、パリから来た男性に「お風呂は何分間利用したらよいのか?」と、質問を受けました。
電気風呂のほかには、露天風呂、檜風呂、薬風呂などがあります。また、タオルやシャンプーなどは自分で持っていく昔ながらのスタイルで、ドライヤーは30円入れて使う懐かしいお風呂屋さんです。
もちろん地元の方が多いですが、外国人も含めて「いちげんさん大歓迎」でされています。
【アクセスなど】
千本鞍馬口バス停から歩いて約5分。
料金は大人430円。
営業時間は、日曜は朝8時〜。それ以外はお昼3時〜。深夜1時まで営業されています。

『仁和寺にある法師、年寄るまで、石清水を拝まざりければ、心うく覚えて、ある時思ひ立ちて、ただひとり、徒歩よりまうでけり。』という徒然草の有名な一文を古典で習った方も多いのではないでしょうか?
京阪・八幡市駅前の男山の山上にある石清水八幡宮は、平安時代前期860年に清和天皇が創建しました。それ以来、都の裏鬼門、つまり南西の守護として、また武運の神様として源氏に信仰されていました。現在の社殿は、徳川家光によるものです。
2016年には、本殿だけでなく舞殿や楼門、廻廊など10の建物を合わせた「本社十棟」が国宝となりました。
さて、石清水八幡宮は、年間の祭事が100を越える多さでも有名で、その中にはエジソンにゆかりの祭事があります。
1879年にエジソンは最初の白熱電球を発明しました。フィラメント(電球の中の針金みたいなもの)に木綿糸を炭化させたもの使い、40時間点灯する事に成功しました。エジソンはもっと長い時間使えるようにと、紙や糸、植物の繊維など数々の材料から試作を繰り返し、その数は植物の種類だけでも6000種類以上といわれます。
ある日エジソンは日本からのお土産の扇子を見つけ、その骨を使って電球を試作しました。すると、電球の寿命は飛躍的に延びました。その扇子の骨は竹。竹は繊維が太く丈夫で、長持ちするフィラメントを作るのに最適だったのです。さっそくエジソンは「究極の竹」を求め世界中に研究員を派遣し、その中で京都を訪れた際、竹の名産地であった八幡の「八幡竹(はちまんだけ)」を紹介されました。この竹を使用した電球は何と平均1000時間以上も点いたそうです。その後、十数年間、八幡竹がアメリカの家庭や職場、街灯を照らしました。
このエジソンとのご縁を踏まえ、昭和9 年に石清水八幡宮の境内に「エジソン記念碑」が建立されました。エジソンの娘さんは昭和39年に訪れ、「これほど立派な記念碑はアメリカでも見たことがない」と感激されたそうです。
石清水八幡宮ではエジソンを偲んで、毎年エジソンの誕生日である2月11日にエジソン生誕祭が、命日がある10月にエジソン碑前祭を行っています。内容は、記念碑の前で日本とアメリカの国旗を掲げ、日米の国歌を流します。神社の境内に星条旗が上がるのは非常に珍しいことだそうです。10月の碑前祭では、電力関係者によってカーネーションの花輪が捧げられます。
ちなみに、エジソン合格祈願絵馬の素材は竹です。表はエジソンの似顔絵、裏には「1%のひらめき 99%の汗」と書かれています。角形は「合格」の意味です。
八幡市には、駅前にエジソンの銅像やエジソン通りがあるなど、竹とエジソンゆかりの地です。
【アクセス】
京阪・八幡市駅から男山ケーブルに乗って3分。そこから歩いてすぐです。
ケーブルが便利ですが、男山の麓の一の鳥居から本殿まで階段を上がると20分はかかります。仁和寺にある法師の念願を果たしてあげようと思う方は、ぜひ登ってみてください。
【バックナンバーカレンダー】

