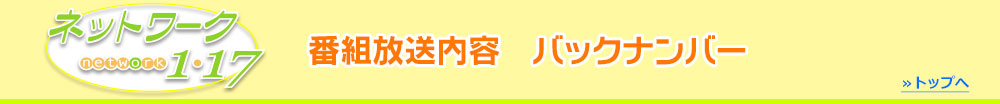10月30日(日)
第1037回「鳥取県中部の地震〜南海トラフ地震との関連は?」
電話出演:京都大学防災研究所 准教授 西村卓也さん
鳥取県中部で今月21日に発生した地震は、活断層が見つかっていない場所で起きました。2000年に発生した鳥取県西部地震も、同じく活断層の無い場所でした。
GPS(全地球測位システム)を使った最新の地殻変動研究を進める京都大学防災研究所の西村卓也准教授は、山陰地方に、地震を発生させる地盤の“ひずみ”が蓄積している可能性があることを以前から指摘していて、今年7月に番組に出演した際も言及していました。ひずみが蓄積している場所では、活断層が見つかっていなくても大地震が起きる恐れがあるということです。
今回、鳥取県中部で発生した地震によって地盤の“ひずみ”に変化はあるのか、近畿地方でひずみが蓄積している場所はどこなのか。また、近い将来発生するといわれている南海トラフ地震と相次ぐ内陸地震との関連性について、西村准教授に聞きます。
千葉猛のひとこと
近畿にも鳥取県中部の地震と同じく「ひずみ」がたまっている場所があります。南海トラフのみならず、内陸型の地震にも備えなければなりません。「緊急地震速報」は揺れる前に届くので戸惑ってしまいがちですが、ラジオやテレビ、メール等で知ったらすぐ命を守るための適切な行動をとりましょうね。
10月23日(日)
第1036回「鳥取県の地震最新情報/熊本地震から半年〜神大生が故郷で奔走」
取材報告:野村朋未キャスター
21日(金)に鳥取県中部で発生した地震について、最新情報をお伝えします。
一方、熊本地震は発生から半年が経ちました。
神戸大学2年の寺本わかばさんは生まれ育った熊本県西原村で住民の手助けに奔走しています。
西原村は熊本地震で大きな被害を受けた地域です。地震直後、故郷に戻りその被害を見たとき、自分が離れたところにいる訳にはいかないと1年間大学を休学することを決めました。
その寺本さんを西原村で野村朋未キャスターが取材しました。
西原村で寺本さんは「週間DOGYN(どぎゃん)」を発行しています。行政の情報をわかりやすく説明し、再建のための制度を高齢者にもしっかり伝えようと始めたものです。梅雨時には雨漏り対策など生活が少しでもよくなるような情報を集め、村のお祭りや行事を掲載し村で何が起こっているのかを知らせてきました。その情報誌を寺本さんは手配りすることにこだわっています。被災者と顔を会わせて話をすることから、寺本さんのボランティア活動はどんどん広がってきました。
一人ひとりが抱える問題に寄り添い、その力になろうとする寺本さんの姿からボランティアとは何なのかあらためて考えます。
野村朋未のひとこと
今回の取材で私の中でのボランティアの概念も変わって来ました。
まず”何かしなくては"ではなくて、”何か出来ることはありますか?"の気持ちでボランティア出来るといいなと思います。
いつボランティアを必要とする日がくるかわかりません。
普段から”相手の声を聴き気持ちに寄り添うこと”を心がけておきたいものです。
10月16日(日)
第1035回「阿蘇山の噴火による影響/熊本地震から半年〜益城町のいま」
電話出演:「かんぽの宿阿蘇」 総支配人 柏田弘利さん
電話出演:益城町で被災した前田七郎さん
熊本地震の発生から半年が経ちました。
復興に向けて進む中、先日阿蘇山で爆発的噴火が起き、これからの観光シーズンに大きな影響が出ています。
阿蘇山の北東に位置する「かんぽの宿 阿蘇」では、敷地内に噴石や火山灰が積もり、一時休館にして、職員総出で敷地内の噴石などを片付けに終われました。いまは、営業を再開していますが、12月までですでに800人のキャンセルがでているということです。総支配人の柏田弘利さんは、震災後6月まで休館し、ようやく客足が戻ってきたところでの噴火は大きな痛手だと話します。
また、2度の震度7を観測した益城町では今月末には避難所が閉鎖されます。仮設住宅は1492戸建設され、現在のところ1394戸入居しています。また、賃貸住宅を仮設住宅とみなして家賃を補助する「みなし仮設」の申し込みも1257件あるということです。
益城町で自宅が全壊した前田七郎さんは、その後も仮設住宅に応募するも抽選が外れて、今も、経営する熊本市内のダンス教室事務所で生活しています。
自宅の解体も、件数が多く、復興にはまだまだ時間がかかると話します。
番組では、阿蘇山の噴火の被害を受けた「かんぽの宿阿蘇」の総支配人・柏田弘利さんと、益城町で被災した前田七郎さんにお電話をつなぎ、現在の状況と今後について聞きます。
千葉猛のひとこと
前田さんのお話を聞いて、熊本地震の被災地の倒壊家屋の解体が地震発生から半年たった今もほとんど進んでいないことに改めて驚きました。また阿蘇の噴火の影響を受けた観光支援も踏まえて、これからこそさらに多くの人が熊本に行って、自分の目で被災地の様子を見ることが大切ではないかと感じております。
10月09日(日)
第1034回
「リスナーのお便りから〜自宅で介護をしている人は災害にどう備えればいいの?」
ゲスト:同志社大学 教授 立木茂雄さん
今回は、番組に寄せられた1通のはがきから防災を考えます。
堺市にお住まいの70代の女性から届きました。「夫の介護をしていますが、災害が起きたら私一人で夫を車いすに乗せて逃げることは無理で、もうあきらめています」というものでした。
この女性のように、高齢の夫婦だけの世帯や自宅で介護を行っているという世帯は年々増加しています。
では、どうすれば災害から命を守れるのでしようか。
東日本大震災以降、全国の自治体では災書時要援護者名簿の作成が進められています。
自分たちだけではどうにもできない場合、周囲の人に助けを求める方法です。
では、要援護者名簿は災害時に生かされているのでしようか。また、支援を必要とする人は、名簿に登録さえすれば安心なのでしようか。名簿登録の他にできる防災対策とはどんなことなのでしようか。
災害時要援護者の支援に詳しい同志社大学の立木茂雄教授をグストに迎え、在宅介護者や高齢者世帯の防災を考えます。
野村朋未のひとこと
要援護支援者名簿が活かされたお話を聴き「名簿に情報をのせても・・・」と半信半疑だった方も
少し考えが変わったのではないでしょうか。
”あきらめないこと”
共助を引き出す自助をと立木さんがお話しされていた通り自分だけで何とかしようとせず
人に助けを求めてお互い助け合う気持ちを持ちあえればと思います。
番組をお聴きの皆さんの声からみんなで防災を考えるきっかけをいただきました。
これからも皆さんの声をお届けください!
10月02日(日)
第1033回「水害に備える〜福知山市の豪雨災害対策」
取材報告:MBS 千葉猛アナウンサー
電話出演:福知山市観音寺自主防災会会長 小滝篤夫さん
8月末に国土交通省が1000年に1度の大雨を想定した「洪水浸水想定区域図」を発表しました。
3年前の台風18号、2年前の集中豪雨と2年連続で市街地が浸水するという大きな被害が相次いだ福知山市では、
この新しい想定図で、新たに洪水や浸水区域が増えることになりました。
水害が多い福知山市は、盆地で水はけが悪く、市街地の中心部を流れている由良川にカーブが多いため氾濫しやすいほか、それにより由良川に続く用水路の水が溢れ、街のいたるところで浸水がおこりやすいということです。
市ではこの2、3年の被害を受けて、排水ポンプの増設などの治水対策を進めていますが、市街地を離れたところでは
大雨で浸水する地区も数多くあります。
各自主防災会では、市のハザードマップ以外に、自分たちの地域独自の防災マップ作りに取り組んでいます。
地元の人ならではの地域の特徴をマップに盛り込んでいき、各家庭に配布を行っています。
きょうは福知山市の観音寺地区自主防災会会長の小滝篤夫さんに、自主防災会の取り組みについてお話を伺っていきます。
千葉猛のひとこと
「車の避難所」を始め、水害の続く地域ならではの独自情報が載った防災マップは他の地域でもぜひ参考にして欲しいです。
地図はA3サイズでラミネート加工されています「大きいからチラシに混じって捨てられたりしないし、雨でも持ち出せます」と自主防災会長の小滝さん。
細やかな工夫にも感服です。