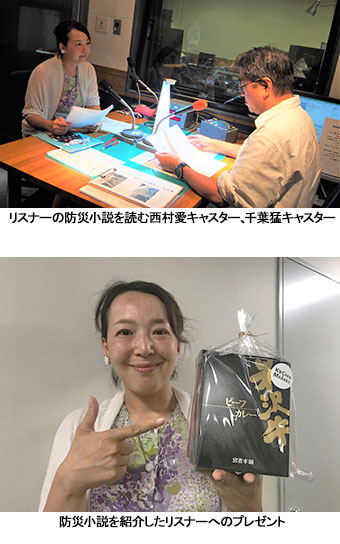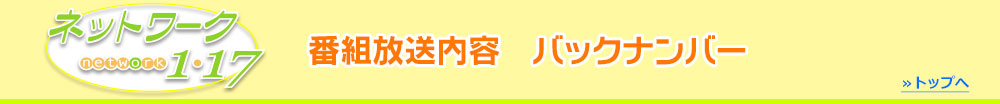06月30日(日)
第1182回「リスナーのみなさんの『防災小説』を一挙紹介」
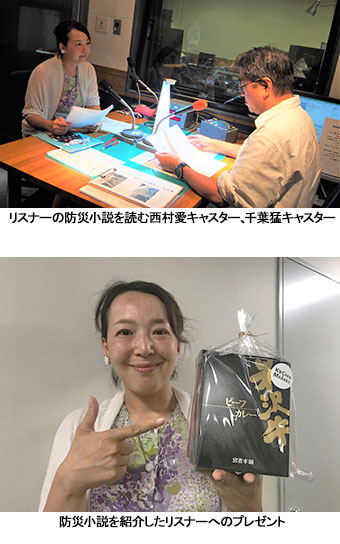
地震が起こったら自分はどう行動するかを想像して綴る800字の「防災小説」を、リスナーのみなさんから募集したところ、たくさんの作品が寄せられました。今回は、6月の火曜日の朝8時40分、小雨が降る中、震度6強を観測する地震が発生したという想定で、書いていただきました。
防災小説は地震学者の大木聖子さん(慶応義塾大学環境情報学部准教授)のアイデアで、災害を他人事ではなく「自分ごと」として想像してもらうのが狙いです。
津波が来ると予想して近所のお年寄りを助け出して逃げる話、電車の中で激しい揺れに襲われ車内が大混乱する話、断水と停電の状況で寝たきりの母親の介護をどうするか悩む話など、作品はバラエティに富んでいて、どの文章も自分と周囲の状況を真剣に考えて書かれたことがよくわかります。そして、文章を書くことで新たな気づきがあり、災害への備えを見直したというリスナーが多かったのも印象的でした。番組では、キャスターが選んだ作品を紹介しながら、地震への備えをあらためて考えます。
西村愛のひとこと
それぞれの防災小説を朗読していると、新たな気づきが沢山ありました。災害を他人事ではなく、自分の事として考えて書いてくださったからこそなんだと思います。千葉アナウンサーと私も書いてみました。改めて備えていこうと実感しています。お忙しい中、参加してくださったみなさまありがとうございました!
06月23日(日)
第1181回「大阪北部地震1年~なくならないブルーシート」
取材報告:新川和賀子ディレクター

今月18日で大阪北部地震から1年が経ちました。5万7千棟の住宅が被害を受け、その内99%が「一部損壊」でした。被害は軽微だったと感じるかもしれません。しかし、1年経った今も被災地には、補修が終わらず屋根にブルーシートがかけられた住宅が残っています。修理が進まない要因はなんでしょうか。
ひとつは、屋根瓦を補修する業者不足です。近年、瓦の需要が減り、職人が少なくなっています。また、去年9月の台風21号で大阪ではさらに被災家屋が増え、ますます業者不足となりました。もうひとつの要因は、経済面です。「一部損壊」は、国の支援金の対象外で、自治体の独自支援も最大20万円に過ぎません。屋根瓦の補修や壁の張り替えなど、工事費用は数百万円かかるケースも多く、住宅の補修をあきらめる人が少なくありません。
専門家らは、「支援の対象枠を広げてはどうか」「一部損壊の定義を見直すべき」といった声をあげています。大阪北部地震から1年後の同日に起きた山形県沖を震源とする地震でも、多くの住宅が屋根瓦に被害を受けていて、被災者の再建を後押しする施策は喫緊の課題です。大阪府高槻市を取材した番組ディレクターが、被災者の声から見えてきた現状と課題を報告します。
千葉猛のひとこと
「こういう状態がいつまでも続くと暗い生活になってしまうんでね」という被災者の言葉が耳に残りました。修理が進んでいない住宅の調査は、行政としてすぐに始めるのは難しいのかもしれませんが、せめて家の修理に踏み切れない高齢者のいまの様子を見に行き、お話を聞くことは早急に始めてほしいです。
06月16日(日)
第1180回「大阪北部地震1年~ブロック塀は改善されたのか」
取材報告:千葉猛キャスター

昨年6月18日に発生した大阪北部地震では、高槻市で小学校のブロック塀が倒壊し、登校中の9歳の女の子が犠牲になりました。この学校のブロック塀は高さ3.5メートルで、建築基準法が定める「高さ2.2メートル以下」という基準をはるかに超え、塀を支える「控え壁」もありませんでした。この事故を受けて、高槻市は全ての小中学校と公共施設のブロック塀を撤去することを決めました。
民間のブロック塀はどうでしょうか。ブロック塀の耐震基準は、1978年の宮城県沖地震など、犠牲者が出るたびに見直されてきましたが、新たな基準に合わないからといって、撤去や改修が義務付けられているわけではありません。そのため、現在の耐震基準を満たしていないブロック塀は非常に多く存在します。
大阪北部地震の後、避難路沿道の一定規模以上のブロック塀については、所有者が耐震診断を行うことが義務付けられました。診断や撤去の費用を補助する自治体も増えています。大阪北部地震から1年で、ブロック塀対策は進んだのか、千葉猛キャスターが報告します。
西村愛のひとこと
私達にできることは何か。それを考えて実践することが、まわりの人たちの未来にもつながることを実感しました。今回のリポートでは国土交通省が出しているコンクリートブロック塀のチェックポイントのご紹介もありました。専門家に相談する事も一つの方法。自治体の補助制度があるかの確認も忘れずに!
06月09日(日)
第1179回「地震を起こす大阪湾の海底活断層」
ゲスト:神戸大学教授 海洋底探査センター・センター長 巽 好幸さん

最大震度6弱を観測した大阪北部地震は、どの断層が動いて大きな揺れになったか断定できず、未知の断層の可能性も指摘されています。大阪湾は今も沈降を続けていて、それに伴う未知の活断層が数多く存在します。大阪湾の底を走る「大阪湾断層帯」は、神戸市沿岸から大阪湾南部まで約40キロ延び、マグニチュード7.5程度の地震を引き起こす可能性が想定されていますが、それ以外の海底活断層の調査は進んでいません。
神戸大学は来年、大阪湾の海底活断層の大規模調査に乗り出します。「反射法地震探査」という方法で、船舶から圧縮空気を海底に撃ち込み、人工的に地震波を発生させて、その跳ね返り方のちがいで地下の構造を調べます。
同大学海洋底探査センター長の巽好幸教授は、一般の人に関心を持ってもらうため、クラウドファンディングでこの調査の資金を募っています。空気圧縮機やボンベのレンタル代など目標額は200万円です。大阪湾の海底活断層とその調査について、巽教授に聞きます。
クラウドファンディングサイト「academist(アカデミスト)」
地震を起こす海底活断層を、大阪湾全域で探査する!
https://academist-cf.com/projects/111?lang=ja
千葉猛のひとこと
陸にあるものは海の底にもあります。大阪湾の活断層が動けば大地震も津波も起きる可能性があるんです。いつ動いて地震が起きるかわからないのですから、活断層の場所を知るための調査は大切です。巽さんのクラウドファンディングにご興味のある方は、ぜひリンクしているホームページをご覧くださいね。
06月02日(日)
第1178回「土砂災害のリスクを知り、命を守る」
電話:京都大学 教授 小杉 賢一朗さん

6月は梅雨入りの季節、そして土砂災害防止月間です。昨年7月の西日本豪雨では、最も被害が大きかった広島県で土砂災害による死者が87人にのぼりました。
土砂災害は近年、増加傾向にあります。昨年、全国で発生した土砂災害は3,459件で、1982年の集計開始以降、過去最多を記録しました。増加の要因として考えられるのは、雨の降り方の変化です。短時間に局地的に降る猛烈な雨や、降りはじめからの総雨量が1,000ミリを超えるような記録的大雨が各地で降り、土砂災害をもたらしています。山林と住宅地が隣接する地域では砂防ダムの整備が進められていますが、追い付いていないのが現状です。
番組では、各地の土砂災害現場を視察し斜面崩壊の研究をすすめる京都大学の小杉賢一朗教授に電話をつなぎ、近年の土砂災害の傾向や適切な避難のために必要なことを聞きます。
西村愛のひとこと
近年、増加傾向にある土砂災害。小杉さんは『土砂災害は、非常に個別性の強い災害』だと話します。住んでいる場所が土砂災害に対して弱い場所かをチェックする。もし避難するなら、どの道を通ると安全か。避難するタイミングも含めて、『もしもの時を考える』想像力が大切だなと思いました。