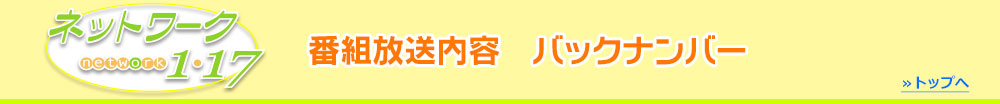ゲスト:NPO法人「よろず相談室」理事長 牧秀一さん

神戸市のNPO法人「よろず相談室」の牧秀一理事長は、阪神・淡路大震災の発生直後から被災者の話に耳を傾け、寄り添い続けてきました。震災が発生したのは、定時制高校教諭だった44歳の時。避難所で、被災者の相談にのる「よろず相談室」を開設し、被災者向けの情報を掲載した新聞も発行しました。避難所解消とともに解散したものの、仮設住宅での孤独死や自殺が相次ぎ、活動を再開。取り残される被災者や高齢者をなくそうと丁寧に訪問して話を聞いてきました。震災10年を過ぎてからは、地震で心身に障害を抱えた「震災障害者」の支援にも奔走。行政が実態調査に乗り出すキッカケにもなりました。
震災発生からまもなく25年。被災者も高齢化し、多くの死に直面し続けてきて「しんどかった」という牧さんは、来年1月で活動の第一線から退くことを決めています。
「人は人によってのみ救われる」そう話す牧秀一さんをゲストに迎え、25年間の活動と今も残る課題について聞きます。
「絵本作家によるおうえんフェス 2020」ご招待
原発事故の影響を受けた子どもたちを守る「12人の絵本作家が描くおうえんカレンダー」
参加の絵本作家による
ライブペインティングや読み聞かせのイベント「おうえんフェス」
http://12ehoncalendar.com/index.html
に、大人10人、子ども10人をご招待します。
「おうえんフェス希望」というタイトルで、
おところ、お名前、電話番号、参加希望の人数(大人何人、子ども何人)を書いて、
メールかハガキでご応募ください。
【宛先】
メール:117@mbs1179.com
ハガキ:〒530-8304 MBSラジオ ネットワーク1・17「おうえんフェス」係
締め切り 12/1(日)
当選者には、番組から直接ご連絡します。
千葉猛のひとこと
阪神淡路大震災の被災者に寄り添い続けて25年。そのきっかけは避難所での若者の言葉だったんですね。この25年間、継続して活動を続けてこられたメンバーは牧さん1人だけだったそうです。いまも被災者の方の苦悩は続いています。牧さんの思いを若い人が継いでいってくれると信じています。