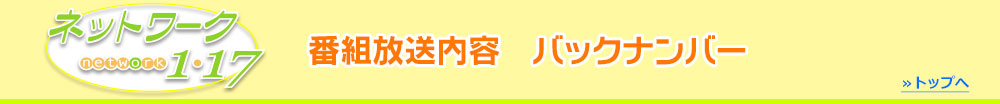オンライン:東京理科大学 教授 桑名一徳さん

マグニチュード7.9の揺れが首都圏を襲った「関東大震災」は、発生からまもなく100年を迎えます。死者・行方不明者およそ10万5000人。その9割が火災による犠牲者で、被害を拡大させたのが「火災旋風」だと言われています。
「火災旋風」は炎が回転しながら燃え上がる現象で、「炎の竜巻」とも言われ、風速や地形などの影響で発生するとされています。関東大震災では、現在の東京・墨田区にあった陸軍被服廠跡の空き地に避難した4万人近くが「火災旋風」に巻き込まれるなどして亡くなりました。
今後、首都直下地震や南海トラフ巨大地震でも、条件がそろえば「火災旋風」が発生する恐れがあります。2011年の東日本大震災でも、宮城県気仙沼市で火災旋風とみられる竜巻状の火柱が目撃されました。火災旋風のメカニズムとその対策について、東京理科大学の桑名一徳教授に話を聞きます。
西村愛のひとこと
今から100年前の関東大震災で発生した"火災旋風" 。炎の竜巻が次々に発生し、襲いかかってくる。あまりにも恐ろしくて言葉を失いました。今後の南海トラフ巨大地震でも、木造住宅の密集地で大規模な火災が起きれば、火災旋風が発生する可能性があるとのこと。桑名さんが教えてくださった対策。私たちにも出来ることがありますよ!