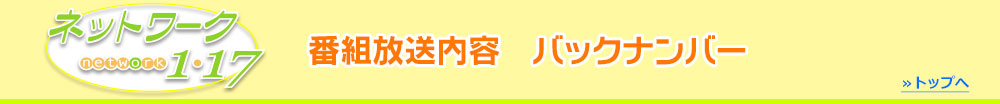01月28日(日)
第1424回「阪神・淡路大震災29年【4】~震災を読みつなぐ」
ゲスト:震災を読みつなぐ会 KOBE 代表 下村美幸さん

6434人が亡くなった阪神・淡路大震災は、今月17日で発生から29年を迎えました。震災を経験していない若い世代へ、震災の記憶と教訓をどう語り継ぎ、次の災害に生かすのかが、これからの課題となっています。
2005年に発足したボランティア団体「震災を読みつなぐ会KOBE」は、小・中学校などで、阪神・淡路大震災に関する手記や詩の朗読を行っています。メンバーは、主婦をはじめ、元教師、元アナウンサーなどさまざまです。
代表の下村美幸さん(72)は、西宮市の自宅で被災しました。当時は自分が生き残ったことを申し訳なく感じていたそうです。しかし、"災害の記憶を絶対に風化させてはいけない"との強い思いから、「震災を読みつなぐ会 KOBE」を発足させ、今も活動を続けています。番組では、阪神・淡路大震災に関するいくつかの手記を紹介し、次の世代への語り継ぎについて考えます。
震災を読みつなぐ会KOBE
https://www3.hp-ez.com/hp/yomitsunagu/
令和6年能登半島地震災害義援金
三井住友銀行 赤坂支店
口座番号:(普)9830511
口座名 :「JNN・JRN共同災害募金」
JNN・JRN共同災害募金では、この災害で被災された方々を支援するため、
みなさまからの義援金を受け付けています。
義援金は全額、日本赤十字社を通じて被災地に届けられます。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/925674?display=1
西村愛のひとこと
『震災を読みつなぐ会KOBE』では、様々な方から託された手記を読み伝えるだけではなく、子どもたちが自ら読んで伝えてもらう取り組みをされています。震災が"過去の出来事"→"自分ごと"へ変化し、ご家族やお友達と話すキッカケが生まれています!!素敵な活動ですね。私も参加したくなりました!
01月21日(日)
第1423回「阪神・淡路大震災29年【3】~阪神・淡路大震災29年の神戸で」
オンライン:「1.17KOBEに灯りをinながた」実行委員
FMわぃわぃ 総合プロデューサー 金千秋さん

1月17日、神戸・東遊園地の「1.17のつどい」では、参加者のさまざまな思いを聞くことができました。沖縄・今帰仁村から初めてこの場所を訪れたという70代の女性は、神戸市中央区で働いていた弟を亡くしました。「体が動くうちに一度は来たいと思い、きょうだいで相談して思い切ってみんなで沖縄からやって来た。感無量だ」と涙を流しながら語りました。「能登半島地震の映像を見て、参加したいと思い、初めて来た」という小学生とその両親にも出会いました。震災29年の神戸は、能登半島の被災地に思いをはせる一日になりました。
番組のゲストは、「1.17KOBEに灯りをinながた」実行委員会の金千秋さんです。この行事では、早朝でなく夕方の5時46分に灯篭をともし、黙祷します。仕事や学校からの帰りに立ち寄りやすく、ボランティアの人も関わりやすい時間帯。地元の小中学生がろうそく作りや灯篭並べの作業を担い、高校生や大学生からも語り継ぎの意思を表明するメッセージが発表されました。大勢の人に関心を持ってもらい、若い世代を巻き込むためにどんな工夫をしているのか、FMわぃわぃの総合プロデューサーでもある金千秋さんに聞きます。
FMわぃわぃ
「令和6年能登半島地震」緊急募金
https://tcc117.jp/fmyy/2024%e5%b9%b41%e6%9c%881%e6%97%a5%e7%99%ba%e7%81%bd%e3%80%8c%e4%bb%a4%e5%92%8c6%e5%b9%b4%e8%83%bd%e7%99%bb%e5%8d%8a%e5%b3%b6%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%80%8d%e3%81%b8%e3%81%ae%e7%b7%8a%e6%80%a5%e5%8b%9f/
西村愛のひとこと
『1.17KOBEに灯りをinながた』は、金さんをはじめ実行委員の皆さんが、日頃から地域の多様な皆さんとの関わりを大切にされてきたからこそ、多くの若い世代や外国人の方々、障がいのある方も参加して行事が続いているんだなと感じました。3歳から大学生まで震災当時の話を聞き準備を行うことで、自然と地域住民の皆さんとのつながりが生まれているのも素敵ですね。
01月14日(日)
第1422回「阪神・淡路大震災29年【2】~能登半島地震でも明らかになった『進まない耐震化』」
オンライン:元・神戸市職員 一級建築士 稲毛政信さん

発生からまもなく29年を迎える阪神・淡路大震災では、死者の約8割が建物の倒壊などによる圧迫死でした。今年の元日に起こった能登半島地震でも、国の耐震基準を満たさない多くの建物が倒壊しました。高齢者が多い石川県珠洲市の耐震化率は51%と、全国平均の87%を大きく下回っています。耐震化はなぜ進まないのでしょうか。
元神戸市職員で一級建築士の資格を持つ稲毛政信さんは、耐震化の必要性を訴え続けています。阪神・淡路大震災で西宮市の木造・築50年の自宅の2階が崩れ落ち、高校2年生だった長男を亡くしました。稲毛さん自身は離れで寝ていて無事でしたが、被災後、木造住宅について調べ始め、自宅が1981年に新耐震基準が定められる前の建物で強度が弱かったことに気づいたと言います。
阪神・淡路大震災以降、公共施設や防災拠点の耐震化は進んでいますが、一戸建て住宅に関しては、対応が所有者に任されていて、全国レベルで見ると、いまだに1割程度の建物が耐震化されていません。阪神・淡路大震災から29年たった能登半島地震でも露呈した耐震化の課題について、稲毛さんに聞きます。
令和6年能登半島地震災害義援金
三井住友銀行 赤坂支店
口座番号:(普)9830511
口座名 :「JNN・JRN共同災害募金」
JNN・JRN共同災害募金では、この災害で被災された方々を支援するため、
みなさまからの義援金を受け付けています。
義援金は全額、日本赤十字社を通じて被災地に届けられます。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/925674?display=1
西村愛のひとこと
稲毛さんによると、家の耐震改修は、木造二階建て住宅で、診断なども全部合わせて全国平均で220万円ぐらいかかるとのこと。自治体にもよりますが、100万円から150万円ぐらい補助が出るそうです。他にも色んな補助が出るので、実はあまりお金をかけずに家の耐震改修ができる!とのこと。皆さんも検討してみてはいかがでしょうか?
01月07日(日)
第1421回「元日の震度7~令和6年能登半島地震」
電話:映画監督 有馬尚史さん

1月1日午後4時10分ごろ、石川県で震度7を記録する地震があり、東日本大震災以来となる大津波警報が発表されました。地震の規模を示すマグニチュードは7・6と推定され、内陸・逆断層型の地震としては阪神・淡路大震災や熊本地震を上回る規模です。
建物の倒壊や火災が相次ぎ、死者数は120人を超えていますが、安否不明も多く、現在も被害の全容はわかっていません。
番組では、珠洲市で被災し、避難所となった小学校のそばで車中泊を続けている映画監督・有馬尚史さんに電話で話を聞きます。有馬さんは去年5月の能登地震からの復興をドキュメンタリー映画にするため現地に通い続けていて、年末から珠洲市に入っていました。地震の後、避難所の小学校はすべてのライフラインが途絶え、水も物資も届かない状況でした。4日(木)夜になって電源車が到着し、電力が確保されたといいます。余震が続く中、過密状態の避難所で、住民たちが励まし合って過ごしているそうです。現地の状況と必要な支援について、有馬さんに聞きます。
令和6年能登半島地震災害義援金
三井住友銀行 赤坂支店
口座番号:(普)9830511
口座名 :「JNN・JRN共同災害募金」
JNN・JRN共同災害募金では、この災害で被災された方々を支援するため、
みなさまからの義援金を受け付けています。
義援金は全額、日本赤十字社を通じて被災地に届けられます。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/925674?display=1
西村愛のひとこと
2007年から、ここ数年地震に見舞われた能登半島。やっと新しいお家が建ったり、復興の光がみえてきたところに発生した今回の大きな地震。断水していて食料や物資も足りず、手探りで生きる日々。被災地の外にいる人が、情報を提供すると安心につながるということです。今、私たちにできる事を続けていきたいですね。