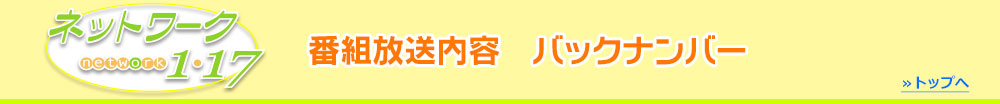07月20日(日)
第1502回「ゼッタイに楽しめない茶道体験」
ゲスト:大阪市港区まちづくりセンター 防災アドバイザー 多田裕亮さん

「大阪・関西万博」の開幕からおよそ3か月。連日、多くの外国人が大阪を訪れています。もし、万博開催中に大きな地震が起こったら、地震や津波の怖さを知らない外国人観光客をスムーズに避難誘導できるのでしょうか。
「ゼッタイに楽しめない茶道体験」は、外国人に日本の伝統文化"茶道"と、突然起こる"地震"を同時に体感してもらおうという新しい試みです。参加者は、畳を敷いた起震車でお茶とお菓子を楽しんだ後、そのまま震度7の揺れを体験することになります。
これは大阪市港区が公民連携で取り組む「おもてなし防災」プロジェクトの一環です。「おもてなし防災」では、英語版の避難誘導ポスターや災害啓発ポスターをつくり、SNSで防災情報を発信するなど、外国人観光客に防災意識を持ってもらい、さらに「外国人の避難誘導ができる市民」を増やすことを目指しています。番組では、このプロジェクトに取り組む大阪市港区まちづくりセンターの防災アドバイザー、多田裕亮さんに外国人に向けた防災対策について話を聞きます。
おもてなし防災(OMOTENASHI BOSAI)
https://omotenashi-bosai.jp/
(番組内容は予告なく変更する場合があります)
07月13日(日)
第1501回「トカラ列島群発地震」
オンライン:京都大学防災研究所 教授 西村卓也さん

鹿児島県のトカラ列島近海で地震が続いています。先月21日以降、今月11日正午までに観測した震度1以上の地震は1800回以上。今月3日には最大震度6弱の揺れを観測しました。この地域ではおととしや2021年にも活発な地震活動がありましたが、今回の地震の回数は過去のケースを大きく上回っています。悪石島や小宝島から多くの住民たちが鹿児島市などに避難しました。
トカラ列島はもともと火山でできた島々。陸側のユーラシアプレートの下にフィリピン海プレートが沈み込んでいる地域です。また、近海には2本の活断層があります。京都大学防災研究所の西村卓也教授は、地下のマグマの動きが活断層を刺激したことが群発地震の原因ではないかとみています。
気象庁は、「震源が浅く、観測点に近いと震度が大きくなる」として、当面、最大震度6弱程度の地震に注意するよう呼びかけています。群発地震の原因と今後の見通しについて、西村教授に話を聞きます。
西村愛のひとこと
今回のトカラ列島の地震は、過去の群発地震と比べて、最大級の地震。マグマの活動が地震の原因の一つとして考えられるそうです。どうなると、群発地震がおさまるのでしょうか?
⇨「マグマが冷え固まってマグマの移動がおさまると地震を起こすことはなくなる」とのこと!住民の皆さんが島に帰れる日が早く来ますように。
07月06日(日)
第1500回「番組1500回~災害時に頼れるラジオとなるために~」
ゲスト:元番組プロデューサー 毎日放送報道情報局 大牟田智佐子さん

1995年の阪神・淡路大震災をきっかけにスタートしたMBSラジオ「ネットワーク1・17」は、今回が1500回目の放送です。災害報道と防災に特化した番組が30年にわたって続いているのは、全国的にみても例のないことです。番組が始まったのは、1995年4月15日、阪神・淡路大震災が起きた3か月後です。当初は、スタッフやパーソナリティーの全員が被災者で、「被災者による被災者のための番組」としてスタートしました。
1998年から12年間、番組のプロデューサーだった毎日放送報道情報局の大牟田智佐子さん(兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科 客員研究員)は、著書「大災害とラジオ」で、被災者に寄り添った災害時の放送を"共感放送"と名付けました。テレビと違って映像がないラジオは、トーク(対話形式)で番組が進行します。パーソナリティーとスタッフ、リスナーとの距離が近く、あたたかいコミュニティが築かれます。大牟田さんは、「"共感"にもとづき、災害時に被災者に直接語りかけることのできるラジオの意義は大きい」と話します。
今年は日本でラジオ放送が開始されて100年の節目です。これから先も、災害時に頼りになるラジオでありたい。1500回目の放送では、大災害とラジオに関する研究を続けてきた大牟田さんに、災害時のラジオの役割と可能性について聞きます。
西村愛のひとこと
番組が始まった頃は、夕暮れ時の生放送。被災した方は、夕焼けを見ながらどんなお気持ちで番組を聞いてくださったんだろうと想像していました。被災した方々からは、『いつもの声をきくことができてほっとした』という声が。これからも、"災害時にもほっとできる、頼りになる番組"を目指して、番組を創っていきます!
06月29日(日)
第1499回「大雨への備え~ハザードマップの見方」
オンライン:備え・防災アドバイザー ソナエルワークス代表 高荷智也さん

本格的な大雨シーズンを迎えたので、今回はハザードマップの見方について、備え・防災アドバイザーで「ソナエルワークス」代表の高荷智也さんに聞きます。
どんなマップを見ればいいのかというときに、高荷さんが薦めるのは、国土交通省の「重ねるハザードマップ」です。日本全国の情報を網羅しているので、自宅だけでなく、職場や学校がある自治体など、複数の市町村にわたる情報を検索できます。さらに、「洪水」と「土砂災害」、「土砂災害」と「津波」など、複数の災害情報を重ねて表示することも可能です。
まずチェックすべきなのは、自分の住んでいる地域が土砂災害や洪水の被害を受ける可能性があるかどうかです。高潮や河川の氾濫で浸水するとしても、どれくらいの深さまで浸水するのかを確認し、自宅の「床の高さ」と比べて、避難の必要があるかを判断します。
大切なのは、災害時に自宅から離れる"立ち退き避難"が必要なのか、自宅にとどまるべきかをまず確認することです。 高荷さんにハザードマップを見るポイントについて教えてもらいます。
西村愛のひとこと
自治体のハザードマップは避難所の情報が載っています。紙のハザードマップは、災害時に停電している時でもすぐ確認ができますね。国土交通省の「重ねるハザードマップ」は、スマホやパソコンで日本全国の災害リスクを確認できます。高荷さんは出張で現地に着いたら必ず"重ねるハザードマップ"を確認しているそうです。それぞれの利点がありますね。うまく活用して備えましょう!
06月22日(日)
第1498回「災害時の偽情報に注意」
オンライン:防災科学技術研究所 総合防災情報センター センター長 臼田裕一郎さん

「来月、日本で大きな地震が起こる」という"噂"がSNSや動画サイトなどで出回っています。この噂に科学的な根拠は全くありません。地震予知や予言は、現在の科学では不可能です。しかし、この噂の影響で、日本への旅行を取りやめる外国人も多く、日本各地の空港で一部アジア地域からの減便が相次いでいます。
"噂"や"偽の情報"は特に、災害時の混乱に乗じて出回りやすくなります。災害時は不安から多くの人が情報を求めます。今は、SNSを通じて情報発信や拡散が簡単に行えるようになり、根も葉もない噂や、偽の情報・画像・動画が出回りやすくなっています。今年4月に長野県で最大震度5弱を記録した地震では、過去の地震被災地の画像があたかも長野県の被害状況であるかのようにXに投稿され、大勢の人の目にふれることになりました。
災害時にSNSから情報を受け取る場合、私たちはどんなことに気をつければいいのでしょうか。災害時の情報の利活用に詳しい防災科学技術研究所総合防災情報センターの臼田裕一郎センター長は、「だ・い・ふく」という言葉を思い出して欲しいと話します。「だ」は、誰が言っているのか。「い」は、いつ言ったのか。「ふく」は、複数の情報を確かめたか。臼田さんに災害時のSNSとの付き合い方について詳しく聞きます。
西村愛のひとこと
まさか、国際災害レスキューナースの辻直美さんの写真が、偽の投稿に使われるなんて!その"まさか"が自分にも起こるかもしれません。私がメディアとして取材するなら、やっぱり現場取材を大切にしていこうと、改めて思いました。偽画像と知らずに拡散をしてしまわないように、『だいふくあまい』をチェックしましょう!
06月15日(日)
第1497回「大阪北部地震7年~帰宅困難者問題」
オンライン:工学院大学 教授 村上正浩さん

最大震度6弱を記録した「大阪北部地震」の発生から、今月18日で7年を迎えます。朝の通勤・通学ラッシュ時に発生したため、電車を降りて線路脇や橋を歩く人の長い列ができました。多くの交通機関がストップして、迎えの車による大規模な交通渋滞も発生。自宅に帰れない「帰宅困難者」が大きな問題となりました。
帰宅困難者対策としては、一斉帰宅の抑制、つまり、むやみに移動を開始しないことが大切です。無理して帰ろうとする人が増えると、歩道や施設の大混雑、「群衆なだれ」など二次災害のおそれもあります。交通渋滞の発生により、緊急車両の到着が遅れるなど、人命を守れないケースにもつながります。
各自治体は、行き場が無くて帰れなくなった人のために、体育館などの公共施設やホテルなどを「一時滞在施設」に定めています。しかし、施設の数は不足していて、災害直後の安全性を誰がどう判断するのかなど、実際の運営には不安も残ります。
大阪北部地震から7年、改めて 「帰宅困難者問題」について、工学院大学の村上正浩教授(都市防災)に聞きます。
西村愛のひとこと
大阪北部地震のときに、みなさんが一時滞在施設の存在を知っていたら、迎えの車による交通渋滞や混乱も少しは減らせたのではないかと思います。家族みんなが安心できるように、備えが大切。『地震が起きたら一時滞在施設や職場に留まるから、迎えに来なくていいよ』と伝えておく。旅先の一時滞在施設を調べておくなど、備えておきましょう。
06月08日(日)
第1496回「"災害ケースマネジメント"を進める法改正」
ゲスト:大阪公立大学 大学院 文学研究科 准教授 菅野拓さん

被災者を個別の事情に応じて支援する「災害ケースマネジメント」は、2011年の東日本大震災で注目を集めた新しい仕組みです。この「災害ケースマネジメント」の実施を後押しする改正災害対策基本法が、先月28日、参院本会議で可決、成立しました。
災害対策の柱となる「災害対策基本法」は、伊勢湾台風を機に1961年に制定され、阪神・淡路大震災や東日本大震災など大きな災害の都度、改正が重ねられてきました。今回の改正では、昨年の元日に発生した能登半島地震の教訓を踏まえ、広域避難の円滑化や、ボランティア団体との連携など災害対策の強化を図ります。
また、被災者支援のための災害救助法には、「福祉サービスの提供」が追加されました。これによって自治体は、高齢者などの要配慮者や在宅避難者など、多様な被災者のニーズに福祉関係者と連携して対応ができるようになります。
番組では、今回の法改正に関わった大阪公立大学大学院文学研究科准教授の菅野拓さんに、法改正のポイントと、「災害ケースマネジメント」の未来について聞きます。
西村愛のひとこと
被災者を支える自治体のみなさんも、被災者。災害を経験していない方も多いなかで、自治体だけで支援するのは本当に大変です。一方で災害支援の経験が豊かな団体や専門家がチームになって、被災者を支えるのは心強いですね。今回の法改正が『災害ケースマネジメント』が全国に広がる大きな一歩になりますね!
06月01日(日)
第1495回「災害時に役立つ井戸」
オンライン:大阪公立大学 教授 遠藤崇浩さん

昨年の元日に発生した能登半島地震では、水道施設が広範囲で壊れ、3か月以上断水した地区もありました。災害時に水が不足すると、健康被害や衛生環境の悪化にもつながります。飲料水は支援物資や給水車を通して比較的手に入りやすいのですが、入浴や洗濯などに使う"生活用水"も避難生活には欠かせません。そこで能登の被災地では、自宅の庭や工場、個人商店など、地域にある「井戸」から井戸水をくみ上げて"生活用水"を確保したというケースが多くありました。
「井戸」は地震の影響を受けにくく、発災直後から利用できる貴重な水源です。石川県七尾市では、能登半島地震の発生当日から井戸水を利用したという例もありました。それらの井戸は近隣住民に開放され、断水が解消されるまで、多くの被災者の生活用水として役立ったそうです。
しかし、災害時に活用できる「井戸」は一体どこにあるのでしょうか。災害時に利用可能な井戸を登録し、情報共有する仕組みを設けている自治体もありますが、まだ全国的に広がっているとはいえません。災害時の井戸水利用に詳しい大阪公立大学の遠藤崇浩教授に、井戸の重要性とその課題についてお聞きします。
西村愛のひとこと
能登半島地震で被災した友人に「1番困ったことは何やった?」と聞くと、「水が出ないこと!雪をバケツに貯めて、溶けた水でトイレを流したり、食器を洗っていた」と話していました。大都市だと人数が多いので、飲料水の支給も足りないかもしれません。近所で災害時に開放してくれる井戸があると、心の余裕にもつながりますね。
05月25日(日)
第1494回「災害時の停電に備える」
オンライン:名古屋大学 減災連携研究センター 特任准教授 小沢裕治さん

先月、スペイン全土とポルトガルの一部で大規模な停電が発生し、交通機関の運休や通信障害など、約6000万人が影響を受けました。2018年の 「北海道胆振東部地震」によるブラックアウトなど、災害時には大規模な停電が発生する可能性があります。3月に発表された「南海トラフ巨大地震」の被害想定では、発電所や送電網が地震や津波の被害を受け、40都府県の2950万戸が停電すると推測されています。
停電になると、冷蔵庫や洗濯機・照明機器など多くの家電が使えなくなります。暑さ対策はクーラーや扇風機など電力に頼る部分が大きいため、猛暑の際には熱中症も含めた二次被害も予想されます。
スマートフォンは消費電力が大きく、1日で使用できなくなります。連絡や情報収集手段として重要な役割を果たすので、位置検知などの不要不急な機能を停止して省エネモードにするなど、電源を長持ちさせる工夫が必要です。
災害時の停電に対し、どういう備えが必要なのでしょうか。ライフライン防災に詳しい名古屋大学減災連携研究センターの小沢裕治特任准教授に聞きます。
西村愛のひとこと
寒さは、上着やカイロで調整できますが、暑さは服装調節だけでは難しく、扇風機が欲しくなりますね。熱中症対策にも必要です。
◎携帯のモバイルバッテリーは、家族分用意する。
◎非常用電源は充電して普段から使っておかないと、いざというときに、動かない!
ということもあるそうです。普段から家族で使っておくと、安心につながりますね。
05月18日(日)
第1493回「熱中症の正しい対処法」
ゲスト:救急救命士 窪田陽平さん

気象庁の3か月予報によると、5月から7月の気温は全国的に平年より高くなる見通しです。特に、毎年5月は、25度を超える夏日が増え、急に暑くなります。この時期は、体がまだ暑さに慣れていないため、熱中症への十分な対策が必要です。
熱中症は、高温多湿の環境下で体温調節がうまくできない場合に、体内に熱がこもり発症します。初期症状は、めまい・ふらつき・手足のしびれ・吐き気など様々で、重症化すれば脳にダメージを与えて後遺症が残ったり、最悪の場合は死に至るケースもあります。こまめな水分補給や暑さ対策、室内でもエアコンを使用するなど、適切な熱中症対策を行ってください。体の小さい子どもや体温調節機能が低下している高齢者は特に注意が必要です。
もしも、身近にいる人が熱中症になってしまったら、私たちはどのように対処すればいいのでしょうか。番組では、元消防士で救急救命士として多くの熱中症患者を搬送してきた一般社団法人BYSTANDERの窪田陽平さんを迎えて、熱中症患者への対処法について詳しく聞きます。
↓エンディングでご紹介↓
西宮市100周年記念事業 にしのみや⾳楽祭〜MIYAON〜
https://www.shimatakada.com/
(高田志麻さん公式HP)
西村愛のひとこと
*身近にいる人に熱中症の症状が出てしまったら・・・
①声をかける②涼しい場所へ避難させて③体を冷やし④水分・塩分を補給させる。
*体を冷やすポイントは
氷のうや凍ったペットボトルで、首・わきの下・足の付け根を重点的に!手のひらや足の裏を冷やすのも効果的なんですね。会話ができなければ、迷わず救急車を呼びましょう!